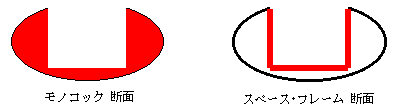
歴史の逆戻り
西洋史、もしくは西洋諸国によって入植された土地の文化史を見ると、戦争における概略の傾向としては、
棍棒 → 刀 → 弓 → 鉄砲 → 大砲 が武器の変遷となるらしい。ところが日本の場合、ザビエルが鉄砲を
持ち込み、信長が鉄砲によって信玄を打ち倒し、鉄砲については生産に到るまで何一つ不自由がないところに
きたのに、江戸時代になると再び刀に戻ると同時に国内に戦が無くなった。これは西洋人の歴史学者にすれば
現在も興味尽きない研究テーマなのだそうだ。
1963年にロータスがF1にモノコック方式を持ち込んで以来、スペース・フレーム方式は廃れていくが、
何故にモノコックがもてはやされるかと言えば、スペース・フレームに比べて高い強度が得られるから
である。
モノコックは外骨格あるいはモナカの皮という言葉で説明されるが、補足を加えるとスペース・フレームが
従来工法の木造建築とすれば、モノコックは柱を撤去し、壁材に力を受けさせる2×4建築のようなもので、
柱に比べて、強度部材が大きい分だけ応力を分散できるので剛性が高い。F1のボディの場合は、言わば
鯉のぼりの中に設置されている数枚の仕切り壁が力を受けている。下図は赤い部分が強度部材である。
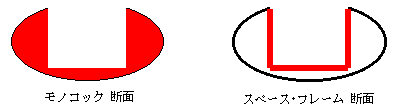
1960年代のスペース・フレームでは、チャンピオン・データでも 300 kg・m/deg 程度だが、当時のモノコック
は 400 kg・m/deg もあり、当時としては大きなアドバンテージだった事だろう。
フェラーリでは、モノコック化はロータスに大きく溝を開けられたが、それはそれとして、1973年になると
フェラーリ初のフル・モノコックのモデルとなる 312B3 が出た。尤もこのモデルはラジエーターを前に置くか
サイドに置くかで揉めたあげくにシーズン中に何度かラジエーターを移設する。驚くべきは、これ以降の流れ
としてモノコックでいくのかと思いきや、次の 1974年モデルは従来のセオリーに基づくセミ・モノコックに
戻してしまう。この時から 312T3 に到る5年間は、外見上、非常に似通った、あのフェラーリ・スタイルと
なり、セミ・モノコックは 1981年の 126C まで継承される。

フェラーリ 312T (カウルを外した姿)
コクピットのカウルとインダクション・ポッドが一体化された上部カバーは、当時としては新素材の
グラス・ファイバーで作った。この時は非金属系の樹脂材料を強度部材に使用する発想はなかったようだ。
(Fulcrum 著)