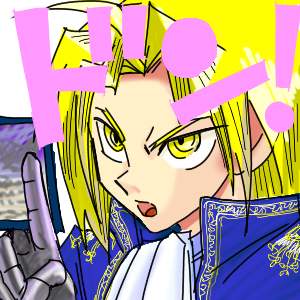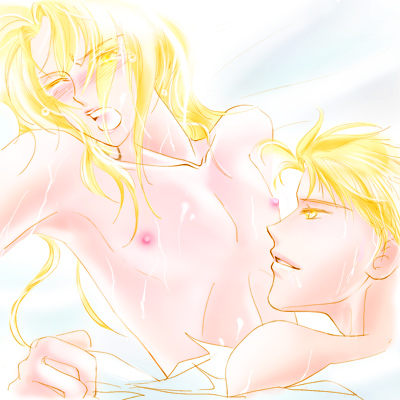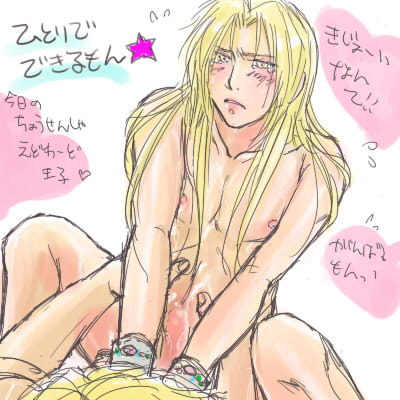|
僕の名はアルフォンスという。アメストリス王国の東部に位置するこのリゼンブール村の、ある落ちぶれた貴族の館で、まるで間借りするような肩身の狭い暮らしをしている、まだ16歳になったばかりの将来有望株だ。
僕の実父マスタングはこの館の主だったが廃れた家名に縋るだけの無能な男で、正妻であった僕の母親が亡くなった後、家名と僅かばかりの財産目当てに近付いてきたコブ付きの年増女ラストに入れあげた挙句、今ではすっかりこの女に家の実権を奪われほぼ軟禁状態でいる。
そして不本意ながらマスタングの実子であるこの僕もまた、ラストとその連れ子であるエンヴィーとグラトニーからいびられ、まるで召使のような扱いを受けているのだった。
「アルフォンス!?アルフォンス!!何回呼ばせるつもりなの?ワタクシに呼ばれたら、どんな時だろうとすぐに来なさい!」
ネットリいやらしい年増女が、胸元が広く空きすぎて乳首が見えそうな下品なドレスを引きずりながら、僕を呼びに部屋までやってきた。
「はい、すみませんお義母様」
僕はうんざりしながらも従順に返事をする。些か癪に触るが、こちらが大人になって下手に出ておけば、少なくともこの馬鹿なオンナが不快な金切り声を上げることがないからだ。
「愚図愚図するんじゃないよ、このドラ息子!お城で開かれる舞踏会に着て行くドレスを選ぶんだからね!さっさとクロゼットからアタシらのドレスを全部持って来るんだよ!」
育ちが悪い為、普段は『ワタクシ』という一人称が少し油断しただけで『アタシ』になってしまうのだ。ああ・・・見苦しいったらない。
でも僕はそんな内心などおくびにも出さず、にっこり笑って対応する。
「はい。いますぐ」
言いながら急いで踵を返し、衣裳部屋へと向かいながら独りごちた。
「嫌だなぁ・・・あのヒトたちのファッションセンスったらギャグでも勘弁して欲しいレベルなんだもの。それを真剣にああでもないこうでもないってとっかえひっかえ必死に選ぶ様子を傍で見ていなきゃいけないなんて・・・・・途中で笑ってしまわないように気をつけるのは相当キツイよなぁ」
*らく*
いくつかある衣装の中から、継母はよりによって一番有り得ないだろうという一着を選んだ。
シルクの生地を紫色に染め上げたドレス。
鯨の骨で出来たパニエで目一杯スカートを膨らませてみせているその部分には、真緑色の薔薇の花が咲き乱れ、真っ黄色な蝶達が乱舞している。
ありえないその配色にアルフォンスは目眩がしたが、「髪飾りを持ってきて頂戴!」と命じられ、彼女のお気に入りの赤い羽根飾りを渡してやる。
上から下まで、隙がない程にチグハグだ。いっそここまで完璧なら、誰にもその趣味の悪さを突っ込まれたりはしないだろう。
「うわぁ!お母様、またスゲーの選んだんだねぇ・・・・・・ククク。いや、似合ってるよ。うん。」
そうやって自分の母親の色彩感覚のズレを分かっているくせに、面白がって煽るのは長女のエンヴィー。
その彼女から、アルフォンスに鋭い声が飛んでくる。
「おい!アルフォンス!早く俺達のドレスも持って来い!いいか?俺のは、あの真っ黒いドレス。グラトニーのは、サンドベージュにストライプのやつがあっただろう?早くしろ!!」
エンヴィーはそう口汚く命じてきた。家ではこんなでも、必要とあらば楚々とした口調と態度で猫も被る。この家の中では一番の狡賢さを誇る人物だ。
希望通りのドレスを持って行ってやると、すぐに二人の娘はそれに着替えた。
次女グラトニーは何も考えずに、サンドベージュに細い茶色の横ストライプが入ったドレスに身を包んでいる。
彼女の膨れたパンパンな球体のような体型に、その伸びたストライプのドレス姿はどこから見ても歩くバウムクーヘンにしか見えない。
これは、どう考えてもエンヴィーの策略だ。
今日のお城の舞踏会には、あのエドワード王子も出席するのだから一人でもライバルは減らしたいところなのだろう。
王子エドワードはこの国では絶大な人気を誇る。アルフォンスは本人をこの目で見たことはないが、長い金髪と金色の瞳は自ら輝くように美しいと聞く。
それに国民の為にと日々心を砕き、民の声にも真摯に耳を傾ける良き皇太子であるという。
「おら、ボサッとするな!もう出かけるんだから、早く靴を用意しろ!お母様のはオレンジ色の、俺のは黒、グラトニーのは茶色のだ!」
アルフォンスは言われるままに希望通りの靴を出してやる。
エンヴィーは真っ黒のドレスに黒い靴と自分だけバッチリ決めたつもりらしいが、そのドレスは胸部分とスカートがセパレートになっていて、彼女の腹は丸出しである。
エンヴィーはスレンダーな自分の体を見せ付ける為に露出したいのかもしれないが、舞踏会に臍を出して行くというその場違いな下品さ加減には気がついていない。
「じゃあ、アルフォンス!アタシらが出かけている間もしっかり働くこと!サボルんじゃないよ!!」
そして三人は我こそがエドワード王子の心を掴むのだと、意気揚々と出かけて行った。
その色々と残念なセンスを持ち合わせている三人を送り出すと、家に一人残されたアルフォンスはやれやれと溜息をついた。
*山崎ぱいんさん*
「ああ・・・・・・マジうぜェ・・・・・・・」
俺が生まれ育ってきた、そして今なお取り巻く環境は、ハッキリ言って俺のシュミじゃない。
兎に角装飾過多としか表現しようのないゴテゴテキラキラとした城が俺の生まれ育った家で、その一角にある俺の部屋も例外なく、同じようにゴッテゴテのキラッキラだ。しかし、ウザったいのはそれだけじゃなかった。
例えば窓辺に置かれた長椅子で横になってこんな風に本を読んでいれば、必ずどこからともなく『じいや』がやってきて、俺の所作にケチを付けてはさめざめと泣くのだ。鬱陶しい事この上ない。
「王子!またそのような品のない。我が王家にふさわしき品格と威厳をいかなる時もお忘れなきようにと爺はいつも申し上げておるではないですか!皇后様譲りの折角の美貌が台無しでございます・・・・・嗚呼・・・・お痛わしや・・・・!」
「王子のくせして皇后譲りの美貌で悪かったなコノヤロウ!俺が気にしていることを毎日毎日毎日毎日言うんじゃねえ!!」
いつまでもわざとらしくハンカチで目許を押さえている爺やに持っていた分厚い書物を投げつければ、年寄りにあるまじき超人的な動きでひらりとかわされ、俺はまたギリリと歯ぎしりをした。
物心つく前から今までずっと世話になっている爺やのフーは体術の盛んなシン国の出身で、実は俺のボディガード兼護身術の師匠でもあるのだ。
「確かに、お気になされるのもごもっとも。その美貌が仇となり、『自分よりも美しい王子の許への興入れなど以ての外』とこれまで何度お妃候補に逃げられたことか・・・・・・嗚呼・・・・まっことお痛わしや・・・・!」
「やかましいわ!」
さらに大袈裟に泣き崩れる爺やにうんざりした俺が、遠乗りにでも出かけようかと立ち上がれば「お待ちなされ」と止められた。
「ンだよ。ちょこっと気晴らしに馬でも乗りたい気分なんだよ俺は!」
「なりませぬ。本日は夕刻より、アメストリス国中から妙齢の女子を呼び寄せての舞踏会がございますれば・・・・・王子にはそこで、次なるお妃候補を探して頂きますぞ」
初めて耳にする事実に俺は仰け反る。どおりで朝から城の様子が慌ただしい訳だ。俺に知らせてしまえば逃げられる事を想定した父上母上の策略に違いない。
扉の前で爺やに肩を掴まれ、さてどうやって逃げようかと頭を捻っている俺の目前でその扉が開くと、そこには護衛の兵達がわんさか待機していた。最低だ畜生。
色狂いの義母と義姉達がどこか勘違いした装いのままいそいそと城へと出かけた後、僕は誰もいない屋敷で嬉々として窮屈なメイド服を脱ぎ捨てた。
このアメストリス王国には風変わりな習慣があり、王族以外は誰もが皆、例え男でも女性と同じ服を身にまとい生活する決まりがある。お陰で男女の性差や区別の観念があやふやで、男が勝手に自分を女性だと公言したりすることも珍しい事ではなかった。
この風習。元を辿れば、古くからこの地に住まう悪霊から身を守るために男である事を隠したというのが始まりだと聞くが、僕はただ単に、かつての国王の趣味の隠れ蓑だったのでは・・・と、ひそかに思っている。
とにかく、まともな精神をした僕には耐えがたいこのドレスを脱いで男子の服を着れる貴重なチャンスだ。取って返した衣裳部屋で、適当なドレスを見繕うと(勿論義母や義姉の物だ)目の前の床にそれを置き、合わせた両手をそのドレスに触れさせた。
数秒間青く発光したそれは、やがて光が消える頃には男性用の衣装に形を変えていた。
さて、問題はそれらを全て身に付けた後に起きた。
義母が持って出掛けた筈のピルケースが、コロンと床に落ちていたのだ。ピルケースは、義母の『必殺アイテム付け黒子』が入っている大事なものだ。これを片時でも手放そうものなら、それこそ半狂乱になってその後10日間は僕に八つ当たりをするのだ。
「チッ・・・・・あのアマ、どうしようもない・・・・・仕方ない。届けてやるか」
厨房から持ちだしたカボチャを門の外に転がして、また合わせた両手を触れさせれば、あっという間にシックなデザインのオートモービルに早変わりだ。これからの時代、馬車なんてもう古臭い。まだまだこの国には数台しかないモノだけれど、僕の知識と魔法の腕前を持ってすればさしたる苦労もなく出来あがってしまう。自分で自分の才能が恐ろしい。
被っていた長髪のカツラを取れば、僕の髪はとても短く清潔に切り揃えられているし、何より男の恰好だ。義母や義妹にはばれる心配はないだろうとそのままオートモービルに乗り込み、城までの道を走らせた。
*らく*
「はあ・・・・・・・・・。」
俺は逃げるように自分の席へと戻ると崩れるようにそこへ腰掛けて、もう舞踏会が始まってから何十回目かも分からない溜息をついた。
次から次へと様々な女にダンスを申し込まれ、断ることも出来ずに何度もステップを繰り返し、女をリードしてダンスをした。
それにしても相手の女の中に、やけに俺よりも背が高く筋骨隆々だったりする奴が目立つのは気のせいか・・・・・・?
しかもそういう奴に限って俺の尻などを、ダンスに乗じて触ってきたり、首筋に鼻を寄せてクンクンとされたりして、おぞましい事この上ない。
「エドワード王子様。ワタクシと一曲踊っては下さいませんこと?」
やっとダンスの輪から逃れて来たというのに、また俺の席の前までやってきて手を差し出す女にうんざりした目を向ける。
紫色に緑の薔薇と黄色の蝶の極彩色のドレス、真っ赤な髪飾りとオレンジの靴の黒髪の女だ。
他の女に比べると、かなり良いセンいってるぜ。
そのセンスには高評価を与えるが、しかし俺は若い娘にも、ましてや年増の女には更に興味がなかった。
しかも、左目尻と右頬と左の口元に付け黒子は、お前それは付けすぎだろう?
心の中だけでそう突っ込みつつも、余所行きの困惑顔を浮かべて「すまないが、ちょっと休ませてくれないか・・・・・・」と口にしかけたのだが、その年増はぐいぐいと俺の腕を引っ張りやがる。
今のその女の姿勢だと豊満な胸の谷間が丸見えで、オマケに乳首まで零れ落ちそうになっているのを目撃してしまい、俺の気持ちは更に萎えた。
と、そこで会場からざわめきが沸き立つのが聞こえてきて、目の前の女と俺もその声のする方に目を向けた。
金の短髪に金の瞳のやけに男前な青年が、女に囲まれて戸惑ったように立っている。
すらりとした長身に男物の衣装がやけに煌々しく目に映る。しかし俺の知る限り、その男は王族ではないはずだ。
「あいつ・・・・・・誰だ・・・・・・?」
「ああ、あの方が誰だかは存じませんが、先程ワタクシの家の使いの者に頼まれたと言って、忘れ物を届けてくださった方でございます。」
俺が思わず零した呟きに、目の前の女がそう答えた。
そして、その女が目を離している一瞬の隙をついて、チャンスとばかり俺はそっと椅子から立ち上がると、その場から脱兎の如く逃げ出した。
*山崎ぱいんさん*

*しおみんさん*
継母の忘れ物を届けに来た途端、ボクはゴテゴテと着飾った女性達に取り囲まれた。
「ちょ、あの…」
「どちらの方ですの?私と踊ってくださらない?」
「ずるいわ!私とよ!?」
…ったく…女ってどうも苦手だ。
継母といい、姉といい、何だってこう煩いのか。
「ごめんなさい、届け物をしに来ただけだから…」
まるで獲物を取り合うハイエナのような女性達に、精一杯の笑顔を向けてボクは群れの隙間をすり抜けた。
「おい!そこのお前!」
誰かに呼び止められて振り向くと、素晴らしい刺繍を施したシャツを身に纏った金の髪の青年がこっちへ向かってくる。
どこかの貴族だろうか。
上等な身なりのその人物に腕を掴まれ、顔を覗き込まれた。
「お前、どこのやつだ?見た事ねぇな…」
近くで見ると金色の瞳が美しい。
一目でボクはその人に引き込まれ、暫く魅入ってしまった。
そんなボクに怪訝そうな表情になった相手に、はっと我に返り慌てて返事をする。
「あ、あのっ…アルフォンスと言います」
「アルフォンスか…」
「あなたは…?」
「あら、あなた、何仰ってるの?こちらの方がエドワード様よ?」
「ええっ?」
割って入ってきた女性に告げられた真実に驚きを隠せない。
この人が…あのエドワード様?
確かに人を引き込む美しい姿態に、輝くばかりの金の瞳に金の髪。
艶かしいその人を、その時すでにボクは、心の奥底で手に入れようと企んでいたかもしれない。
「エドワード様、踊っていただけませんか…?」
*花菜さん*
彼を見た瞬間、僕は恋に落ちた自分をハッキリと自覚していた。
自覚した一瞬後には、彼がこのアメストリス王国の国民の敬慕の念を一心に集めているあのエドワード王子だという事実を知ったけれど、そんなものは僕にとって何の障害となるものではなかった。
恋という局面に際し、男はすべからく狩人であるべきだというのが僕の持論だ。相手があのエドワード王子ならば、なおさらだ。
先手必勝とばかりに此方からダンスの誘いをすれば一瞬だけ戸惑ったような表情を見せたものの、直ぐに勝気な光を宿した瞳をキラリとさせて、不敵な笑みで手を差し出してきた。
「面白ぇ。お手並み拝見といこうか?」
同性・・・・それも男同士でのダンスだ。よってファーストコンタクトは勿論、どちらが男性パートを受け持つかという熾烈な争奪戦に始終した。しかしそこは身長差と(恐らく)経験値の差で難なくねじ伏せた僕が危なげなく手に入れ、物騒な雰囲気こそ拭えないものの、何とか自分が望んだ形でダンスへとなだれこむ事に成功した。
会場は、あろうことか男である珍客と王子が手に手をとり踊り始めた光景に一同唖然としていたが、僕もそしてエドワード王子もそんな事などまったく意に介さなかった。
なせならこれは、命を掛けた大勝負なのだから・・・そう・・・・まさしく、喰うか喰われるかの戦いの最中に僕たちは居たのだった。
*らく*
俺はハッキリ言って、軟弱なやつらはシュミじゃない。
初恋は、今でもはっきりと覚えているが、アームストロング少佐だった。あのたくましい筋肉と体躯、武術の腕、そして豪放磊落な性格。まさしく男の中の男!って感じだ。
しかし、少佐は駐在武官として国外へ赴任してしまい、俺は、失恋に泣き暮らした。
この国は、おかしな風習が色々あることから分かる通り、キホン軟弱な気風でなりたっている。おれは王子としてそんな国のあり方に、一石を投じたいと思い続けてきた。
まずは俺が王になったら、国民全て、性別どおりの格好をさせてやる。おかしな性癖の持ち主や、怠惰な風習、それに奢侈に流れる生活態度も全て取り締まる。逆らうやつはみな粛清だ。
そんな俺が、くだらないお后選びなどに興味をもてるはずもなかったが……。この、目の前にいる男は、今まで俺の知らなかったタイプだった。
短く切った髪、若々しく、まだ幼さが残るものの、男らしい顔立ちと、十分将来性を確信できる体躯。
どきんとした。
それにこいつは、よりによって俺に「踊っていただけませんか…?」と言ってきた。つまりこいつは、俺を落とそうとしているのだ! オスの目つきで。
最高だ……!
俺は燃えた。いい度胸じゃねえか。やってみろ。必ず返り討ちにしてやる。俺のベッドへ押し倒して、あんあんいわせてやるぜ。
*KKさん*
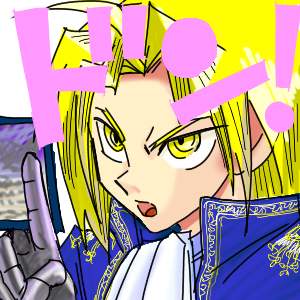
*みなもさん*
固唾を飲んで見守る人々の輪の中心で、流麗な円舞曲の旋律に乗りつつ、僕と彼は激しい主導権争いを展開した。
身長差ゆえやむなく女性側のパートに甘んじているものの、さすが王族というだけはありダンスの場数は相当なものらしく、なんとホールドした手の僅かな動きだけでこの僕をリードしようとするのだ。甘い眼差しで見つめれば、蕩けるほど優美な表情が台無しの肉食獣のようにギラつかせた目を向けてくるし、その足元では鬼のようにステップとターンを繰り返しながら此方の足を掬おうと常に油断のならない動きをみせている。
嗚呼なんてスリリングな恋の攻防・・・・!
鬱陶しい義母義姉にばれないようにと夜な夜なこっそり屋敷を抜け出して、その先々で落した女の子の数はちょっと人に言うには憚られる程の僕だ。そろそろもっと歯ごたえ・・・・もとい、手ごたえのある相手を求めていたところだったから、この彼のやんちゃぶりには身震いがくるほど燃えた。
なんという落し甲斐のある相手だろうか。この強気な瞳を官能の涙で潤ませてやりたい。このストイックな唇から、甘い喘ぎを引き出してみたい。その真珠のような素肌を暴きつくしてしまいたい。
喉を鳴らしながら、彼の華奢な背に回していた手に力を込めた時だ。
「ククク・・・・・・ッそんな獲って喰いたそうな目をこの俺様に向けてくるとは・・・・・命知らずなヤツ。勘違いすんじゃねぇぞ?」
生まれながらにして王座に居る人間ならではのオーラを放つ彼は、妖艶な笑みを浮かべながら僕の襟もとのタイをグイと引っ張ると、キスをするのではという距離にまで顔を近付け言った。
「喰う側にいるのはお前じゃねぇ。俺様だ。体格差で勝ったつもりでいるようだが、俺様のテクの前に跪くがいい・・・・!!」
自分が組み敷かれることなど想像すらしていないらしいこの美しい王子に、僕の征服欲が大いに刺激された。
さあ、どんな方法で落そうか・・・・・?夜はまだ、始まったばかりだ。
* らく*
細い腰に手を回し、一見僕が引き寄せているように見えるその中身は、若く美しい王子が雌豹のように鋭くぎらぎらした瞳でこちらを挑戦的に見上げていた。ふと持ち上がった腕の、透き通るように磨きぬかれた白く細い指先で、彼はじらすようにこちらの顎のラインをくすぐった。
「何処の誰か知らねぇが、随分と活きのいい玩具だな。退屈で死んじまうかと思ったが、今夜は久々に洒落た趣向を楽しめそうだ」
僕の腕の中でそっと囁くと、彼はその身を後ろへ大きく引いた。柔らかな上体が弓のように仰け反り、金色の豪奢な髪が床に流れる。僕はしっかりと彼を支え、甘く流れるワルツの音楽にあわせてゆっくりと引き戻した。
「失礼しました、エドワード王子」
再び顔が近づく。肌で温められ、僅かに香りの変化したシックなコロンは実に彼に似合っていて、ゆらりと僕の鼻を掠めた。
「エドでいい」
薔薇のように赤く瑞々しい唇が呟いた。
「しかし僕は身分も低く、そのような失礼を貴方には……」
「うるせぇ。俺がいいって言ってんだからおまえはただ従え。……おまえの名はアルフォンスだったな。アルでいいか?」
「はい、エドワード王子……」
「エド、だろ?」
「……エド」
僕の戸惑いを交えた肯定に相手は悪戯っぽくにこりと微笑んだ。その表情はまるで発情期の猫そのものだった。ここまで色香に溢れた人物が、まさか自国の王子だったなんて想像すらしなかった。僕は内心彼の行動の一つ一つに一々どきりとさせられた。
「ほら、俺を上手にリードしてみろよ。うまくやれたらキスくらいは許してやるから」
しかし、軽々しく口にしたその言葉に僕は思わず眉を寄せた。
この人は自分の価値をわかっていない。
そう直感し、それは僕の中にあった、理由のわからない怒りの部分に火をつけた。
「では、僭越ながら今しばらくお相手をさせていただきます」
しっかりとその腰を抱き、もう一方の手で彼の指を軽く握ると、僕は片足を前に滑らせ、王子の身をさりげなく引き寄せた。相手のやや面食らった様子が伝わったが、遠慮する気はもう起きなかった。
指先で彼の身をくるくると操り、なだらかに抱き寄せながら舞踏会の会場内を大きく回った。見かけではわからない、実際は強引だった僕のリードに負けじとその腕が押し退けようとしたけれど、完全に無視して踊り続けた。暫くすると少しずつ、王子の体に疲れが表れ、僕の動きに仕方なくその身を合わせて来た。僕は表情には出さず、内心ほくそえんだ。
*叶さん*
俺が圧されてている。
ありえない。いまだかつてなかった、こんなこと。
俺を狙うやつはみんな媚び諂う。チヤホヤされるのがずっと苦痛で、俺が王子じゃなかったらこいつらは同じ言葉を果たして口にするんだろうか、本心はどこに隠されているんだろうと、そういう人間ほど信じられなかった。
俺を狙う人間同様、アルの目はギラギラしていたが、そこには偽りを感じさせるようなものが潜んでない。
負けるか、と闘志を燃やしていたのに、いつの間にか俺は、勝つか負けるかとか、どっちが押し倒す方でどっちが押し倒される方かなんてことをすっかり忘れ、奴の目だけを見ていた。
俺と同じ金色の瞳。策士を思わせるあざとさが見えていたがそれを隠さないところがいっそ潔くて、こんなふうに俺を見つめる人間がいるのが不思議だった。一国の王子を本気で落そうとするとは、なんてバカな男だろう。正気だろうか。……本当に本気だろうか?
この男と踊る前に散々踊り明かしていたせいか、さすがに疲れて脚がもたつき始める。なによりもアルの瞳を凝視していたせいで平行感覚が怪しくなり、いつの間にか俺はヤツのリードに助けられるようになっていた。
ふいにアルが脚を止める。
こっちは急に止まれず、よろけた。
アルは微笑んで繋いでいた俺の手を持ち上げると、恭しく指先に唇を寄せる。
「さっきの約束、覚えていますか? ご褒美を賜りたいのですが」
「え?」
俺の腰を抱き寄せて、ヤツは自分の体に強く押し付ける。さっきからアルの顔を見上げている俺の背は反り返って、自分で重心が取れなくなり、ヤツの腕の中に全身を預けるような格好になった。
我に返った俺は、征服してやろうと思っていた相手に征服されそうになっていることに気付き、その腕から逃れようとしたが、思いのほか逞しくて抵抗らしい抵抗が出来ない。
離せ、と口を開いたが、言葉は出てこなかった。
言葉を発する前に、ヤツの唇で口を塞がれた。
*直さん*
俺だって一国の王子だ。閨での事は一応教育を受けているし、これまでそういった経験がないわけでもない。
しかし、今まで俺は自分から相手を押し倒し服をむしり取って事を進めるという立場しか知らなかったし、当然のことながらそれ以外のスタンスでの対処法を誰からも教わっていなかった。
だから、自分より随分と頭が高い位置にある相手に覆いかぶさるようにされたり、さらに腰に回した手が力強く俺の身体を上へと引き上げる為に殆ど爪先立ちの体勢を余儀なくされたり・・・・・と、こんな状態でキスをすることなど初めてだった。正直、面食らった。
俺たちの周囲にいる大勢の招待客や召使い達は皆唖然とし、楽団は楽器を奏でる事さえ忘れている為、ホールは水を打ったような静けさだった。
「ん、ンン・・・・・・ッんふ・・・・・・・ッ!ム、・・・・・・ハフ・・・・・・んん!」
角度を変えながら密着させたまま一瞬たりとも唇を離さない男は、巧みな舌技で俺の咥内を余すことなく蹂躙し痺れるような耐え難い官能を瞬く間に引き出した。なんというテクニックか。悔しいがこれに関して言えば完全に俺の負けだ。かくなる上は、ベッドの上で一気に形勢逆転を狙う事が唯一残された勝利への道だ。俺は房事の教育係に『貴方様に艶っぽいセリフをお教えしたところで無駄ですから、せめてこれだけは死ぬ気でマスターなさって下さい』と、叩きこまれてきた『妖艶な笑み』をここぞとばかりに披露した。
さあ、俺のこのメロメロスマイルに骨抜きにされるがいい・・・・・!!!
*らく*
俺は上目遣いに相手の視線を捕らえると、両の口の端を上げ、薄く唇を開いて微笑んで見せた。
途端に俺を見つめるアルの金の瞳に欲の色が上塗りされたのが見て取れる。そう、その色だ。そんなふうに俺に捕われているがいい!ここから先は俺様のターンだ!!
「おい!俺は今から寝所で休むことにする!!俺が呼ぶまで誰も来るな!声もかけてくるなよ!いいな!!」
傍にいた召使い達にそう言い置くと、唖然とする客達にも構わず、俺はアルフォンスの腕を強引に引きながら階段を上がり自分の寝所へと連れ込んだ。
ドアをガチャリと閉めると、相手の男に向き直る。そして、その視線に不覚にも一瞬ドキリとしてしまった。
射抜くような金色は先程と同じく俺への欲望の色で彩られているが、その中には不穏な肉食獣のようなギラつきまで含まれている。なんて奴だ。
そして、その視線のままに俺を引き寄せ抱きこむと、再び唇に貪りついてきた。
「む・・・・・・ん・・・・・・はっ!・・・・・・っ!!」
俺の腰にたちまち甘い官能を伴った痺れが走る。マジでこいつのキスは危険極まりない。
このままでは相手の思うつぼだ。俺は力の限りアルの胸を押すと、背後にあるベッドへと押し倒し、素早く彼の上に跨った。
「はは、どうだ?アル?俺に押し倒された感想は?」
俺はアルを見下ろしながら、不敵に微笑んで言ってやる。そして、これ以上待てないとばかりに、組み敷いた相手の上着を性急に開き、その肌を暴いてゆく。
服の下から、予想以上に引き締まった胸板が現れて俺は思わず息を飲む。
逞しい肩口と首筋から鎖骨へのラインは男の色気を漂わせている。
ついで、その見上げてくる瞳は俺の下にいながら、まだ獲って食おうと狙う獣のものだった。
「エド、これで僕を服従させられるだなんて、まさか思ってないよね?」
上半身の肌を晒しながらも、全く余裕の表情でアルにそう問いかけられるのが気に入らない。
俺はそんな往生際の悪い相手に何か言い返してやろうと思ったが、途中でその口は驚きで固まってしまった。
アルが両手を合わせてゆっくりと俺の体に触れた途端、信じ難いことに俺の衣装が全てパラパラと崩れてベッドの上に落ちていき、気がつけば俺は一糸纏わぬ姿にさせられていた。
*ピンクテキストの錬金術師さん*
この何処をとっても匂わんばかりの美しさで満ち溢れている王子だが、その気性はとても一筋縄ではいきそうにない。だが、それだからこそ落とし甲斐もあろうというものだ。
ところが、さてどうやってしかるべき段階へ進もうかと僕が思案するまでもなく、王子みずからお膳立てをしてくれるから驚きだ。
この僕をホクホクと自分の寝所へお持ち帰りあそばすとは・・・・・なんという迂闊な王子だろうか。今までは家臣達があらかじめ篩いにかけた、しっかりと教育され大人しくされるがままになってくれる女性しか相手にした事がないのだろうと直ぐに分かる無鉄砲振りだ。
『やれやれ・・・・・これじゃあ余程手加減してあげないと泣かせてしまうだろうな』と溜息をつきながら、果たしてこの魅力的な獲物を前にして自分の理性がもつのかどうか自信の持てない僕だった。
そうこうしている内に、廊下の最奥にある華美な装飾が施された大きな扉の前にたどり着く。王子はなんとはしたない事に、その扉を蹴り開くと僕を中へと突き飛ばすように誘った。暫くは可愛い王子のしたいようにさせてあげようかと思っていたけれど、そのあまりの魅惑的な様子に僕の中の雄が暴れ出してどうにもならない。手加減することも忘れ、貪るようにその唇を味わう。細い腰を抱き締める手に震えが伝わると、胸の中は彼という人と出会えた幸運を祝福するファンファ−レがけたたましく鳴り響く。
今時こんなに初心な人がいるなんて!それも僕の好みど真ん中の容姿。何より向こう見ずで勝気な態度が堪らない。男であるとか、身分違いであるとか、そんな事は些細な問題でしかない。今、この人を自分のものにしないでおけば、僕はきっと一生死ぬまで今日のことを悔やんで生きていくだろう。
・・・・・そう考えている時点で自分が既に彼の虜になっているのだという事に、僕はまだ気付かないでいた。
「はは、どうだ?アル?俺に押し倒された感想は?」
一生懸命寝台に倒した僕の上に圧し掛かると、命知らずな王子はまだ自分の窮状も知らずに不敵に笑った。嗚呼、可愛い。嗚呼、虐めてしまいたい。
駄目だ・・・・・もう我慢できない。
「エド、これで僕を服従させられるだなんて、まさか思ってないよね?」
いささか反則臭いが構うものか。僕は魔法を使って一気に彼の着衣を全て粉々にしてしまった。
小さな布片へと変化した華やかな夜会用の衣装がはらはらと花びらのように彼の身体から滑り落ち、現れたのは僕が想像していたよりもさらに美しい、玉のような肌だった。
「綺麗だ・・・・・エド・・・・・・まるで天使みたいだ・・・・・・・!」
呻くように口をついて出た僕の声が欲望に掠れていた所為か、王子は急に表情を変え無意識にだろう、傍らにあった薄布を引き寄せた。
「ぶ・・・無礼者・・・ッ!お前、は・・・・・・ただ、黙って俺のされるがままになってれば良いんだ!ア・・・・ッ!触ン、な・・・・・・アッ!?」
頬が緩むのを止められない。
僕が睨んだとおり、これまで王子は『閨では全て王子のされるがままでいるように』と言い含められた人形のような相手としか寝たことがないのだろう。
教えられた手順どおり半ば義務のように行為を行うだけで、彼の身体は他者の手によって与えられる感覚を全く知らずにまっさらなままなのだ。
「大丈夫。僕が今まであなたに誰も教えてくれなかったことを全て教えてあげる・・・・・」
僕に馬乗りになったまま、まだ自分の立場を良く理解していない彼の腰から両手を上に滑らせて・・・・・・胸のまだ幼さを残す愛しい二つの蕾を親指の先で捏ねるように愛撫した。
「ア・・・・・ン!?何だ・・・・・・・ッ、コレ・・・・・・・!?」
たったそれだけで、まるで雷に打たれたように反応する様子に僕はうっそりと目を細めた。
*らく*
胸の先端への初めてもたらされた感覚は、最初こそくすぐったかったが、間もなくジクジクとした快感が電流のような刺激となって、俺の腰と背中を震わせた。
「あっ・・・・・・ああっ・・・んん!!」
「胸だけで、こんなに感じてしまうなんて。とても敏感で可愛い反応をするんだね、エド。ほら、この快感に素直にその身を全て委ねてしまうんだ。」
「ひぁっ・・・・・・くそっ!そん、な・・・・・・お前の好きには・・・・・・あああっ!!」
俺の下に組み伏されているはずの男に胸を弄られて、その部分は赤く固く尖っている。そして、そこを尚も親指と人差し指できつい位に摘まれて、俺の口からは勝手に高い声が漏れ落ちる。
俺ばかりが全裸にされて、俺ばかりが恥ずかしい声をあげさせられるなんて!!
未だかつてベッドで俺様にこんな不埒な行為をしかけてきた奴は一人としていなかった。
王子としてのプライドを捨てさせられる前に、何としてもこの形勢を逆転させなければ!!
俺はその両の先端への愛撫に必死に耐えながらも、アルフォンスの服を更に捲り上げながら告げる。
「アル・・・・・・お前も脱げ。今すぐ全部だ・・・・・・!!」
「・・・・・・仰せのままに。エドワード王子。」
俺に跨られている男は口調こそ素直ではあったが、その胸の尖りを指で擦る動きもとめないままに、いきなり上体を起こすと軽々と俺の体を背中からベッドに縫い付けて、あろうことか俺の肩を片手で上から押さえつけてきた。
「おっ、お前!無礼な!!・・・・・あっ!あああっ!!なっ、何を?!」
「こうしないと服が脱げないので・・・・・・ああ、エド、上から見下ろす貴方は、また美しくも征服欲を掻きたてられる・・・・・・。」
「何を言うか!?このっ・・・・・・っ!!あああ!!やめっ、はああぁぁ・・・っん!!」
アルフォンスは、予告もなしにいきなり勃ちあがりかけていた俺の自身を口に咥え込み、すかさずねっとりと絡みつくような舌を使って、口内で舐めまわしてきた。
あまりの快感に腰が跳ね上がる。こんな場所を他人に舐められたことなど一度もない。こいつは一体、何てことをしてくるんだ!!
しかし、この最も敏感な部分への直接的な刺激は耐え難い快感をこの身にもたらしてくる。
「ひ・・・・・・ああっ!!ふぁああ・・・・・・っく!!」
痺れるような快感に流されまいと眉を寄せて相手を窺えば、アルフォンスは器用にも俺を口に含みながらも、するすると自らの衣服を脱ぎ去ってゆく。
そして俺と目が合うと、不敵そうにその金の目を細めて視線を絡めてきた。それはギラギラとした金色で涎を垂らす狼のように。
負けたくない!この俺が負けるなんて我慢がならない!!
それなのに、舌で舐め取られる俺の中心はこれ以上ないくらいに固く立ち上がり、先端から滲んだ液体で自分のものとアルフォンスの口の周りをはしたなくも濡らしていた。
* ピンクテキストの錬金術師さん*
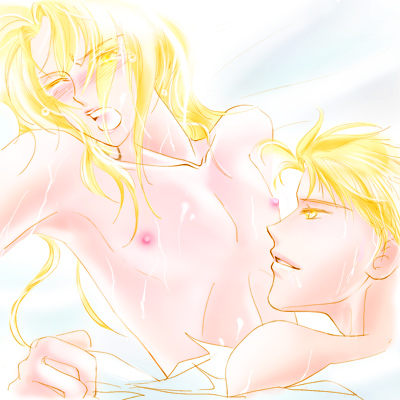
*しおみんさん*
目が離せないでいる俺に自らの視線をその舌のように絡める。獰猛な黄金の瞳を細め、アルフォンスは、殊更ゆっくりと舌を使ってみせた。
こうして衣服を脱ぎ去った目の前の男は、城にある伝説の英雄の彫刻たちのように神々しく美しい。時折覗く白い歯も、薄い唇も、まるで穢れない者のようなのに、それがどうして、こうも扇情的なのか。
ふふっと吐息を洩らして、アルフォンスが、視線もそのままにその真っ赤な口内に呑み込んでいく。
熱く隙間無く蠢く粘膜に、エドワードの限界を更に引き寄せられた。
「ダメ、だっ、っ、ぁあっんんっ」
なんと情けない声だろうか。そう思うのに、喉をせりあがる悦に抗えない。背でシーツが乱れていく。その皺を手繰り寄せて、足を張り、身を捩るが、どうあっても振り払うこともできない。
「…っ、く、そっ!」
エドワードは息を詰め、下肢に絡むその男の咥内にすべてを吐き出してしまった。
収まらぬ高まった呼吸のまま見やれば、アルフォンスが、ニコリと微笑む。母から与えられた飴のように愛しげに唇の名残を舐めた。
「有難く頂戴しました、エドワード王子。」
「お前なぁ!」
怒りにまかせて身を起こせば、明らかにウェイトの勝ったアルフォンスが覆い被さってきて、エドワードは再びシーツへと縫い付けられた。
耳朶に口付けられる。
「そのような大きな声は無粋ですよ。」
熱い舌が吐息と共にくすぐりながらも、唇が食むように耳を辿る。そうして、首筋へとキスを零していく。
少し温度の低い指先が、硬さを失わない胸の尖りを弄びながら、もう片方の掌が、先程熱を放ったばかりのそれへと絡み、然程執着することなく、奥へと忍び込んだ。
ゆるりと、指が意思を持って埋め込まれる。
「無礼者!」
途端、顔色を変えたエドワードが、これまでとは違う勢いで拳を振るい、それをアルフォンスが思わず避けた瞬間に、身を翻した。ベッドにたくさん重ねられていた枕のうちの一つから、短剣を抜き、アルフォンスへ突き向ける。
短剣は、王子のために鍛えたものなのだろう。黄金で細工の美しい柄に紅い宝石が埋め込まれているが、決して宝飾品などではない。
元々緩く結われていた髪が乱れ解けて、肩に流れるようにかかる。
一糸纏わぬ姿で膝を立て、先程まで今にも熔け出しそうであった甘く潤んだ黄金の瞳は、まさに喉元を掻き切る為に飛び掛らんとする猛禽類のようだ。
* 水渡つぐむさん*
屈辱に頭が煮えた。
俺の体をもてあそびやがって……! こんな真似を許したことは一度たりとてない。夜伽の手ほどきをしてくれた、ホークアイ伯爵夫人の言葉を俺は忠実に守ってきた。
「先手必勝よ、王子。とにかく相手の動きを読むの」
結果、俺は常に主導権を握り続けてきた。それが、新参者の年もさほど変わらぬたかが若造に、こんな辱めを受けるなんて……!!
爺のフーに、短刀術は仕込まれている。
襲いかかった俺は、えぐりこむように腹部を狙った。吸い込まれるように、切っ先が届く。
ニヤリ、とアルは笑った。
青白い輝きがほとばしった。さきほど俺の服を剥ぎ取ったのと同じ、魔法の輝きだ。この練成光は古の呪文、この国で、まだこれを使えるヤツが存在したとは。驚いた俺が目を見開くと同時に、短剣はてのひらのなかから、あっというまに消えうせた。そして、紅い宝石や黄金の飾りそのままに、俺の手首を拘束する手枷へと変貌していた。
呆然とする俺をアルフォンスは捕らえ、素早くうつぶせに引き倒した。
「う……くぅ、は、離せ!」
「フフ……さすが一国の王子。その誇り高さ、揺るがぬ矜持……僕は、こんな素晴らしい主君をもつ国の国民だったんだ」
アルフォンスの低い囁きが耳朶を掠めた。
「すてきだね。綺麗な顔や綺麗な体より、あなたの心はずっと美しい」
ぶる、と自分の体が震えた。確かに、アルの言葉は、俺の真芯を揺すぶった。
そのままアルは、耳たぶを口に含み、そっと吸った。背筋に手を伸ばし、ゆっくりと腰までなでおろす。手つきは官能に満ちていて、俺は思わず声を上げた。
「ア……!」
「ねえ、僕は、あなたを手に入れたい。あなたと僕は身分が違う……恐らくこれは一夜の幻で終わるんだろうね。でもそれでもいい。ただ、僕を忘れて欲しくないんだ」
「な……にをいきなり勝手なことを」
俺はよわよわしく言った。いまさらながら思い知ったのだ。俺はこいつのことを何も知らない。
「そうだね」
指先が背筋を辿り、もう一度奥底の部分を触った。一度そうされていたので、今度は驚かなかった。ただ、俺を受け入れる側として扱った人間が、今まで一人もいなかっただけだ。
そのまま、後を追うように唇が耳から離れた。首筋を這い回り、背筋を辿り、吸い上げられた。尻を揉みしだきながら、その間も指先の悪戯は止まらない。俺は、暴れたが、はいつくばらされたうえ、足を大きく広げられ、どうしようもなかった。
そして、舌が―――その部分へ―――――。
「ああ! やめろ!」
舌が割り開き、俺の中へ侵入してきた。ぞくりとその部分から這い上がるものがあった。先ほどの快楽の余韻が、埋火となって奥底に残っている。それが、愉悦に変わるのを、俺は呆然と感じていた。
「ばか! 馬鹿者! 離せ! 俺を誰だと思っている! こんな屈辱……!」
「でも、体は正直だ。ほら」
腰を救い上げられ、獣の姿勢で膝を立てさせられた。そのまま下腹を抱えられ、あまつさえまだ濡れていたおれ自身を、大きな手のひらが包み込んだ。恥ずかしくも、それは既に熱くなり、しずくをこぼしていた。もう一度ゆっくりと扱かれながら、舌先が深く俺の中に侵入した。高い声が思わず上がり、同時に甘く溶けるような快感が腰を焼いた。
*KKさん*
未だ何者も受け入れた事のない彼の秘所を指でグチュグチュと犯しながら、時折柔肌を震わせては身を捩る白い背中に唇を寄せ、そこを伝い落ちる真珠のような汗の粒を舐めとる。彼の身体から湧き出るもの全てが、僕にとっては甘露の味わいだ。
初めてだというのに、今の僕に手加減をしてあげる余裕はあまりありそうにない。だからせめて、相変わらず居丈高な態度を崩さない高貴で可愛い人に、心からのくちづけを贈る。
うつ伏せの彼の背後から顔だけを此方に向けさせる体勢に、くぐもった抗議の声があがったが、綺麗に無視を決め込む。するとやがて僕の目論見通り、彼の身体からはクタリと力が抜けて全てを僕に委ねるようになるのだった。
「オ・・・・マエ・・・・・汚ぇぞ・・!痺れ薬の類を・・・・・」
怒りの為だけでなく真っ赤に染め上げた目許で、殺気を込めて睨んでくる目線をやんわりと受け止めた。
「仰る通り。口移しで少々薬を流し込ませて頂きました。但し、痺れ薬なんて無粋なものじゃあない・・・・・・・・・これは、『愛』という名の媚薬だよ、エド」
* らく*
急速に熱が下肢に集まるようで、もどかしく身体を震わせば、背後から我が物のようにアルフォンスの掌が触れてくる。
「はっ、んん!」
エドワードは、堪らずその手を頼りに自ら腰を揺すった。恥も外聞も、ましてや王子としてのプライドもない。もっと強い刺激が欲しい、そう思えば思うほど、アルフォンスの掌はつれなくなり、確かなものを与えてはくれず、エドワードはすすり泣くような吐息を絞りだした。
その間にも、体内を好き勝手する指は数が増やされる。
時折指先が掠められる耐え難い場所に、堪らず強請れば、首筋から顎に舌を這わせながら、アルフォンスが背後で笑った。だが、決してこれまでの男のそれとは違い、余裕の無さが伝わる。
「貴方の中に、僕をお許しください。」
そうすれば、もうお望みどおり手加減しませんよ。ここもちゃんと可愛がって差し上げます。
見透かすように、中に埋め込んだ指が目的をもって蠢く。
「――――ぁ、あっ!」
思わず声を洩らしたが、再び唇を噛み、シーツへと頬を擦りつけるようにして耐えるエドワードの様子に、アルフォンスも焦れる。少し大胆になったかと思えば、こうして貝のように固く殻を閉じてしまう。
ここまでは強引にやってきた。
しかし、最後は望まれて、彼の中に導かれたい。
恐らく未だ誰も許したこと無い、その中に抱かれたい
* 水渡つぐむさん*
「ああ、気高くも強情で可愛らしい僕の王子。そんな姿はますます僕を煽るだけですよ。ほら、口で貴方が何と言われようが、下のここはこんなに物欲しそうだ。」
そう言いながら、僕は意地悪くも半分程まで指をそこから引き抜いてしまう。
「あぁ・・・・・・。」
固く閉ざしていたその口から、物足りなさを滲ませて思わず漏れたのは、滴るほどに濡れた王子の声。それもそのはずだ、媚薬まで仕込まれたエドの体の中は、その甘い疼きに完全に支配されている。
片方の手で、そのしっとりと湿った背筋に添って指を這わせただけで、ぶるりと背中を戦慄かせ、腋の下から滑らせた指が尖った胸の頂を軽く掠めれば、ふうっ、と息を詰めてビクビクと体を揺らしながら中にある僕の指を締め付けた。
なんて壮絶な程に魅惑的なのだろうか!もう、僕の方こそが限界に近い。
早くこの王子の中に入りたい、誰にも踏み荒らされていないまっさらなその花園を僕の色に染め上げて、僕だけを感じて、僕だけを求めるように作り変えてしまいたい!!
僕はエドワード王子の中に入れていた指を完全に抜き去った。再び王子が物欲しそうな息を零す。
そして彼の腰を支え、ぬらぬらと濡れながら収縮を繰り返しているその場所へ、僕はこれ以上無いという位に勃ち上がり先走りを垂らしている自分のものを押しつけた。
しかし無理に押し込むことはせずに、行きつ戻りつさせながら入り口周辺に刺激を与え続ける。
「エド。さあ、素直になれば貴方に天国の快楽を味わわせてあげるよ・・・・・・。でも、エドが望まないとあげられない。一言、僕が欲しいって言ってくれるだけでいいんだよ・・・・・・。」
「うっ!い、いやだっ・・・・・・オレが・・・そんなっ!」
エドワードは激しく頭を横に振って抗うも、その本人の意に反して彼の腰は、押し当てられた熱い杭を飲み込まんとするように、いやらしく揺れていた。
彼が堕ちるまであと一息か。どうしても僕は聞きたい、この王子の口から。
プライドや理性を全て捨て、ただひたすらに僕を欲しいと強請る言葉を聞き出したい。
「ほら、こんなにここは挿れて欲しいって・・・・・・エド。貴方から言ってごらん?」
「くっ・・・・・・ふっ!そ、そんなこと・・・・・・っ!!」
最後の矜持を守らんと、首を項垂れてその身の内の欲望に逆らっていたエドワード。
しかし、背後からアルフォンスがその熱い塊を奥の入り口に密着させて、またぐるりと回すようにされた瞬間、エドワードの頭の中は真っ赤な欲望の色に染まった。
「ふっ、あああ・・・・・・ンン・・・・・・っ!!!」
* ピンクテキストの錬金術師さん*
不意に僕の下で彼の身体が動きを止め、全ての抵抗を止めた。
ぐったりと投げ出した身体はそのままに顔だけを此方に向け、欲望に染めあげた強い眼差しを向けてくる。
「良いだろう・・・・・この俺様に恐れもなくこのような振る舞いをした事、必ずや後悔させてやる・・・・・・アル、お前の吠え面を眺めながら悠々と杯を傾けるのは、さぞ気分の良いことだろうよ・・・・・・」
それまでの余裕の無さが嘘のようにエドワード王子は挑戦的な笑みを浮かべながら身を起こすと、最初のように僕の身体を押し倒し跨ってくる。
「エド・・・・最初から騎乗位は無茶だ」
「黙れ。この俺様に、やって出来ないコトはねぇ!てめぇはせいぜいマグロのように無様に横たわったまま俺様の身体とテクニックに溺れるがいい・・・ッ!!!」
言うなり、なんとエドワード王子は自らの秘所を片手で押し広げると猛々しく育った僕の怒張の先端にあて、その細腰を沈め出した。慌てたのは僕だ。いくらこの胸の内に滾る熱い想いを遂げたいと切望しても、それは彼を傷つける事と引き換えであってはならないのだ。
「ク・・・・・・ン・・・・・ア・・・・・ゥ!」
「エド!駄目だ・・・!止すんだ・・・!」
「ウア・・・・ッ」
上体を起き上がらせると同時に、苦痛に顔を歪める細い身体をそれ以上沈みこませないように抱きとめる。その全身はワナワナと震え、冷たい汗でしとどに濡れていた。瞬間、僕は自分のこれまでの行いを悔やんだ。
初めてこの胸に火を灯してくれた相手に出会ったからといって、その人に苦痛を強いてまで結ぶ関係に一体何の意味があるというのか。
彼の身体を両脇に差し入れた腕で一度持ち上げ、そのまま膝の上に抱きあげた。それに全く抵抗せずされるがままだった様子に、なお一層僕の中で自責の念が膨れ上がった。
「何故そのような・・・・・・俺の閨の技量が不服とでも言うのか・・・・この、無礼者が・・・ッ!かくなる上は、貴様にどんな罰を与えてやろうか・・・・!」
すすり泣くように罵りながらも、その身体は未だ震えている。
酷い事をしてしまった。けれど、それは戯れや気まぐれなどといった浮ついた気持ちでは決してないのだ。始めこそ、手の届かない高嶺の花を手中にして籠絡する愉悦があったのは否定できない。だけれども、そんな浮ついた気持ちは彼の目を見てしまえばすぐに霧散してしまった。今、僕の胸にあるのは・・・・・・・分不相応は重々承知だが一度だけで良い、この高潔な魂を持った美しい人と結ばれたい・・・・・・ただ、それだけだった。
「エドワード王子、身の程もわきまえず、なんという無礼を・・・・・お詫び致します」
腕の中で小鳥のように震えている王子に、僕は心から詫びた。しかしそれは、自分のしでかした罪量を軽減したいが為にではない。この高貴で清らかな・・・・・そしてどこまでも純粋で強くあろうとする彼の犯しがたい魂を踏みにじってしまった事に対する心からの懺悔だった。
* らく*
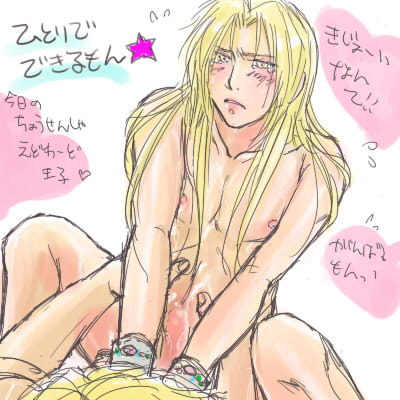
*染さん*
「許さん・・・・・・許さんぞ・・・お前・・・・・アル!」
エドワード王子は自分の表情を見られまいとして、俯いたその頭を僕の胸にぶつける様に押し付けてきた。
その真珠のような白くて滑らかな肩が小刻みに震えているのが伝わってくる。
今までの自分の数々の無礼は、決して許されるようなことではない。
この眩しい程に清らかで潔癖な王子の魂と体の両方を僕は無理に手に入れようとして汚してしまったのだから。
先程までの何としてでも王子を我がものにしようと不埒な画策をして、欲に猛る気持ちは嘘のように僕の中から消え失せていた。
残ったのは、この至高の輝きを放つ王子への畏怖と、尊敬と、止め処なく湧き上がり胸が痛い程の恋情だけだ。
そして今、この胸で震える王子の姿を前にして、自分の仕出かした事の重大さに自らが恐れをなしている。
アルフォンスは、エドワードの長い金糸をまるで宝玉を慈しむように撫で梳きながら、穏やかな声音で話す。
「エドワード王子・・・・・・申し訳ございませんでした。お怒りも当然のこと。僕への処遇などは、王子のお気の済むままに。あなたから与えられる罰ならば、この命が終えるのだとしても何ら悔いなどありません。しかし、最後に僕の心に滾るこの想いを口にして、あなたの耳を汚す事をお許し下さい。」
王子は何も答えはしなかったが、俯いたままに彼がアルフォンスの言葉に注意を向けているのは、ぴくりと揺れた髪先からもしっかりと感じられた。
「王子。僕は一目見て、貴方のその気高い程の美しさに酷く惹かれてしまいました。確かに僕は恐れ多くも、あなたを組み敷いて僕の手によって貴方が欲に染まってゆく姿を見たいだなどと考え、それを強行しようと致しました。しかし、これだけはお伝えしたい。こうして貴方と二人で相対する時間を持つという幸運に恵まれて、僕は本気であなたの事を。王子の穢れのない魂ごと、折れることの無いその強さごと、あなたの事を・・・・・・心の底から愛してしまいました。」
そのアルフォンスの言葉を受けて、そろりとエドワード王子が顔を上げた。その瞳は怪訝そうにやや怒りともとれる金色を帯びていたが、その真意ははっきりとは読めない。
アルフォンスは少しだけエドワードから身体を離すと、金の瞳を伏せてこれが最後とばかりに、再度己の中の感情を口に乗せた。
「愛しています。生まれて初めて僕は人を愛してしまいました・・・・・・エドワード王子、あなたを。」
心の内の感情も全て王子にお伝えした。思い残すことといえば、目の前の愛しい人と最後まで想いを遂げられなかったことではあるが、彼に望まれないのであればそれも仕方ない。
その時のアルフォンスは、もうどんな咎めを受けようとも覚悟はできていた。
無礼者と切り捨てられる覚悟の上で、一国の王子に大胆にも愛の言葉を告げたのだ。
*ピンクテキストの錬金術師さん*
何の前触れもなく転がり込んできた、初めての恋。
これまで僕が数多の女の子達と交わしてきたやり取りなど、これに比べたら些細なものだ。
この世に、こんなにも心揺さぶられる感情があったなんて、僕は知らなかった。まだ出会って幾時間も経っていないというのに、僕の全てが彼に向って引き寄せられていく、抗いようのない猛烈な感情。そして衝動。
この気高い魂を持つ人に、いつもの調子でその場限りの一夜を過ごそうとけしかけた僕は、本当に愚か者だ。そればかりか、迫った挙句この人がその清純で不慣れな身体を自ら割広げようとするまでに追い詰めてしまった罪は測り知れない。
僕は、自分の死をも覚悟した。死罪に処されたとしても当然のことを自分はしてしまったのだから。
ただせめて、最後にこの胸の内を焦がす熱い想いだけは彼に伝えておきたかった。これさえ伝えられるなら、もう死んでも悔いはない・・・・・そう思った。
僕の告白を聞いた王子は無表情のまま、その宝玉のような輝きを放つ瞳を僕に向けて暫し動きを止めた。
僕もまたその目を見返しながら、間もなく来るだろう審判の時を、意外な程静かな気持ちで待っていた。
・・・・と。次の瞬間だった。
王子の頬が、否その首筋や滑らかな胸、指先足先に至るまでの全身が一気に朱に染まったのだ。同時に腕の中にある身体から直に伝わる温度が明らかに上昇するのが分かる。
「・・・・・・・・・ッ」
全身のあらゆる箇所をチェリーブロッサムの色に染め変えた王子は、まるで恥じらうような表情で僕の胸をキリキリと切なく締め上げた。
愛おしい・・・・!!!抱きつぶしてしまいたい・・・!!!
僕の中で、激しく感情が吹き荒れる。
けれど、今の僕にそれは許されない事と、奥歯を噛みしめ自分を制した僕は、努めて感情を表さない声で呼びかけた。
「・・・・・・エド・・・、王子・・・?」
『エドワード』と呼ぶことが躊躇われた僕がそう呼べば、どうしたことか、途端に王子の形相が険しくなり、またしても僕を突き飛ばすように押し倒して馬乗りになって掴みかかってきた。
「“王子”なんて呼ぶな・・・っ!俺が欲しいんだろ?じゃあ、そんな風に俺を呼ぶんじゃねえ!そんな遠くから伸ばした手なんて、俺は欲しくない!・・言えよ・・・・もう一度言え!俺を・・・・・・俺をどう思ってるのか、お前が俺をどうしたいのかを、言え!」
全身を真っ赤にしながら僕の肩を掴んで揺さぶる王子の目からは、まるで氷が溶けだしたように雫がポタポタと滴っていた。それらはとめどなく次から次へと溢れ続け、僕の頬や首筋を濡らす。
「・・・・誰もがそうだ・・・俺を無理矢理高い場所へと押し上げておいて、自分は本心を隠して薄ら笑いを浮かべる・・・・・・それでお前らの何が分かると言うんだ!?何故いつも俺が近付いた分だけ遠ざかるんだ?アル・・・・・・・お前だけは違うと思ったのに・・・・!やっぱり、お前までが・・・・そうなのか・・・?」
*らく*

*花菜さん*
「エド…違うよ………」
ボクはポロポロと涙を零すエドをそっと抱き締めた。
小さい子供をあやすかのように、震える背中をポンポンと叩く。
「ボクはあなたが欲しいんだ。あなたをボクのものにしたい。でも、あなたが無理をしているようで…だから止めたんだよ。無理にして、あなたを傷つけたくないから…」
「………」
「…泣かないで?」
エドの身体をボクから離し涙で濡れた頬を指で拭ったが、透明なそれは後から後から零れ落ちる。
宝石のような涙だった。
「ボクがあなたを望んでもいいと言うなら…手加減はしない」
エドの顎を掴み口を開けさせ、噛み付くように口付けた。
逃げ惑う柔らかな舌を追いかけ、絡める。
角度を変える度に繋がる隙間から漏れる水音が部屋中に響く。
「んっ…ぅ…ン…」
息苦しさになのか、快楽に溺れているからなのか、眉を寄せて必死に何かに耐えている様子をボクは楽しんだ。
抱きしめていた細い肩がブルブルと震え、いきなりエドがボクを突き放した。
「……!アア…!」
びゅるり。
白く濁った液体を花芯から放ち、ボクの腹を濡らした。
精液の匂いが辺りに充満する。
「あ…ぁ……」
「またイッちゃった?キスだけでイクなんて感度いいんだね」
ボーン。
丁度その時、0時を告げる時計の音が城の中に木霊した。
義母や義姉が家に戻る時間だ。
ボクが家にいなかったら大変な事になる。
「ごめん…エド。ボクはもう行かなくちゃ」
「アル?おい、何だよ!?」
素早く身支度をし、呆然としているエドを残して部屋を出た。
まだダンスをしている人達の間を縫って長い階段を駆け下りる。
「アル!!」
愛しいその声に思わず後ろを振り返ると、エドがシーツだけ纏って立っていた。
慌てて追いかけてきたのだろう。
エドと離れたくなかった。
それでも、ボクは帰らなければならない。
数秒の間エドの顔を見つめ、ボクは踵を返した。
「あ!」
ボクのジャケットのポケットからスルリと落ちたそれを、拾っている暇はない。
*花菜さん*
ボクは後ろ髪を引かれながら長い階段を駆け下り、カボチャで作ったオートモービルに乗り込んで城から離れた。
シーツを身にまとった、愛しいあの人の姿が脳裏から離れない。もう二度と会えないだろう。
一夜の夢。
ボクはこの、一夜の夢を胸に抱いて生涯身を焦がし続けることになる、きっと。
あの人を忘れることなんて、出来ない――。
なんとか義母や義姉が帰宅する前に家に帰りつくことが出来たが、エドワード王子に自分たちをアピールできなかったせいで義母たちの機嫌は悪く、キリギリスのように間断なく騒いでいた。キリギリスではなく、縞蚊か。ブンブンと耳元でうるさく煩わしい。
どんな嫌味を言われても、耳を通り過ぎる。心を、あの人のところに置いてきてしまった。
ボクの中は空っぽになってしまった。たった一晩で、ほんの数時間で、これほど埋められない穴があいてしまうなんて。
――エド。
失意の時間をこれからずっと過ごすのかと、会えないであろうあの人のことを狂おしく思っていたら、翌日城から国中におふれが出た。
エドワード王子が一人の男を探している、城の階段に残された、コンドームに合う男を、と。
* 直さん*
市井の人々が、エドワード王子の姿を見る事は、そう多くはない。たいていは新年の挨拶で、バルコニーから手を振る姿を沿道から見るくらいである。なので、今回の舞踏会で、やっと王子が后を迎えるかもしれない、という噂に、国民はこぞって祝杯を上げたのだった。なんといっても美貌で知られる王子である。
さらに首都で成婚パレードがおこなわれるのは確実だ。市民は全員その日を待ち望んでいた。
ところが、エドワード王子が奇妙なふれをだしたのである。しかも、その内容は、とびきり妙だった。舞踏会の日に城の階段に残された、コンドームに合う男を探すというものである。
王子の、美貌に似合わぬ奇天烈な趣味嗜好や振る舞いは、いままでも取り沙汰されていたが、これはまたその中でも、相当におかしな命令だった。幾人もの従者が、王子の命を受けて、街へと飛んだ。全員が、ガラスの棒を持っていた。……一目で男性器をかたどったとわかる、えもいわれぬ容をしていた。そして、大概の男が思わず無言になるほど立派だった。
金髪の男――大体、10代後半から30代前半くらいまで――は、みなその場でズボンを膝までずり下げられ、ガラスの棒と自分の持ち物を比べられた。なかなか合格者はいなかったが。だが何人かは城へ連れていかれた。そして、エドワード王子と対面した。……全員が、噂どおりのその美貌に、魂を宙に飛ばしてぼうっとなった。
そこでさらに選別がおこなわれた。何人かはその場で暇を取らされた。そしてごくごく少数の男が残された……美丈夫ばかりだった。その男たちは一人一人別室に呼ばれ、エドワード王子直々に、下問をうけた。ガラスの棒を握り締める王子に、そこを撫でられ、体を触られる、という、至福と拷問の入り混じったやり方で。
何人かは、我慢できず、王子を襲おうとした。全員が、王子自身の手で叩きのめされた。
王子は、一人の男が半殺しにされて、衛兵の手によって引きずり出されるのを見送りながら、金色の睫毛を伏せ、ガラスのきらめきに桃色の唇を寄せて、憂愁に満ちた溜息をついた。
「違う……」
どの男も、アルではない。
エドワードはちろ、とその先端を舐めた。ガラスはあくまで冷ややかで、あのときの熱さをしのぶことは出来なかった。
*KKさん*

*ゆかいうめこさん*
エドワードの元にその報が届いたのは、もう国中の該当しそうな男は一通り調査を終えたと思われていた頃だった。
たまたま調べに行ったとある貴族の館で、そこで使われている下男もついでに調べてみたところ、ガラス棒のサイズを見事満たしたという。
しかし家のものに言わせると、その人物は普段は女の格好をした召使であり、王子に引き合わすには不相応極まりないだろうと口を揃えた。
それでも城までは連れて来たのだが、その女装の男は選別を行う為に、まずはその男性部分を大きくせよと命じられても頑として拒み続けているという。
「僕の心も身体もエドワード王子のただ御為にのみあります。ですから僕のモノは彼本人を前にしなければ、ピクリとも反応など致しません。調査したければ、王子自らの手によってのみお願い申し上げたい。」
自分の身分の低さも省みず、このようなふてぶてしい態度の女装男の扱いに困り果て、ついに王子の耳にもその話が入るに至った。
「王子、いかが致しましょうか。」
「面白い。構わないからここに連れて来い。」
椅子に肘をついて、その手に持ったガラスの棒の先端を自分の桜色の唇に押し付けて、つるつると滑らかな感触を楽しみながらエドワードは命じる。
正直、俺は女装するような男に興味はない。全くこの国の悪慣習にはくそくらえだ!しかし、国中探し回っても見つからないのだから、ここは自分の趣味をとやかくいっている場合でも無くなってきた。
あいつ・・・・・・俺の心の底を揺さぶったままで消えた男・・・・・・アルフォンス。あれからというもの、俺の頭の中は寝ても醒めてもあの男のことばかりだ。
人間の心理は、逃げられると更に欲しくなってしまうもの。今のエドワードはまさにそれだった。
あいつは挿れろとこの俺が言ったのにも関わらず、途中で止めて挿れなかった。最近では、何となく損をした気分にすらさせられている。
あの溶かされるような唇の感触も、自分を堕とさんとギラついて絡む金の視線も、熱く要所を攻める器用な指先も全て、全て手に入れなくては気がすまない。あれはもう全て俺のものだ。
「チッ!」
そのガラスの棒のくびれの形を呈した部分を唇の先で食み遊び、王子は小さく舌打ちをした。
「エドワード王子、件の男をお連れしました。いかが致しましょう?」
「ああ、ここまで通せ。」
エドワードはガラスのそれを口で弄ぶ姿勢はそのままに、その男が部屋に通されるのを観察する。
大抵の男達はオドオドしながらこの部屋へ足を踏み入れたものだったが、この女装男はまるで慣れてでもいるように部屋の中へ進み入ってきた。
長い金髪はカツラなのだろうか。女装の割にはみすぼらしい召使用の服装が、やけに立派な体躯を無理無理に覆っている。
「おいお前、もっと近くまで寄れ。まずは、俺にその顔を見せろ。」
その声を受けて、その人物はつかつかとエドワードの前に歩み寄り、跪いてからその顔を上げた。
!!!
エドワードは瞬間息を飲んだ。
同時にその透き通ったガラスの塊は足元の絨毯の上に落ちて転がった。
*ピンクテキストの錬金術師さん*

*しおみんさん*
「アル・・・・・フォンス・・・・・・ッ!」
俺の心をかき乱すだけかき乱し、ろくな理由も別れの言葉も残さずに姿を消した男が、とうとう目の前に現れた。これまで只々躍起になってその行方を捜していた俺だが、いざその本人を目の前にしてしまえば、今度は何故あれほどまで必死にこの男を探していたのか、その自分の気持ちが分からなくなった。
憎んでいるのか、それとも恋焦がれているのか・・・・。
自分の心だというのに、まるで何も分からないまま・・・・・ただ、情けなくも何ごとかを口にしようとすれば擦れた吐息しか出てこない。
暫く黙ったまま互いの目を見合っていたが、やがてアルフォンスは静かに立ち上がると、胸の前で合わせた両手を自らの身体に触れさせた。するとそこからまばゆい光が生じ、その身に纏っていた衣装がみるみる形を変えた。
光が消え、あの日と同じ出で立ちへと姿を変えたアルフォンスは、俺が先程取り落としたガラスの棒をつい、と拾い上げながら口を開いた。
「王子・・・・・これは、賭けでした・・・・・。あの日、あなたと過ごしたあの短い時間で、僕はこの命と引き換えにしても良いと思うまでに貴方を愛してしまった。けれど、貴方はいずれこの国を統べる立場にあられるお方。一方自分は片田舎の落ちぶれた貴族でしかない。あの日の事は、例え一夜限りの夢だとしても身に余る僥倖です。が、僕は一度でも貴方と交わってしまえば自分を抑えきれないと分かった。だから貴方を抱かずに去ったのです」
「・・・・・お前へと繋がる手掛かりを残して・・・・・・か」
「あれは偶然だったけれど、でももし貴方が僕を心から欲してくれたなら、それを手がかりに必ずや僕を探し出してくれると思った・・・・・そして貴方は事実そうした。だから、僕はもう自分を抑えることはしないと決めた。王子・・・いや、エドワード」
アルフォンスは熱い瞳を此方にまっすぐに向けながら、ゆっくりと歩み寄ってきた。そして手にしていたガラス棒を優雅に差し出すと、その涼やかな口許に笑みを浮かべて言った。
「どうか存分に、この僕が本当にあの日の男と同じ人間なのか・・・・・じっくり吟味して確かめて。そして、今宵こそあの夜の続きを・・・」
*らく*
もどかしい衣装など、二人ともとうに脱ぎ捨てた。
寝台の上で仰向けになったアルフォンスの上に乗り、エドワードは熱く固く隆起している彼の部分に唇を寄せる。
ガラス棒のオリジナルのはずであるのに、これは熱を持ちビクビクと脈を打つ。実物と似ているのは形だけだ。
いや、アルフォンスのものは熱くてはち切れんばかりに漲っていて、形や大きさまでも凌駕しているように見える。
「んあっ・・・・・・ぅ!」
アルフォンスの熱に舌を這わせている王子の方が、くぐもった声で啼かされた。
エドワードの自身もアルフォンスの口に含まれて舌で舐めとられている。互い違いの体勢でお互いの熱を愛撫するも、アルフォンスの舌業にエドワードは翻弄されっぱなしだ。
じゅぶじゅぶと水気を含んだ音を立てながら、アルフォンスの口に吸い付かれ、舌で執拗に先端から根元まで弄られれば、先走りで更に相手の口内を濡らす。
「あ、あ、アル・・・・・・アル!!」
自分だけ先にイかされたくなくてその名を呼ぶと、自分の中心から口を離れたアルフォンスがエドワードの顔を覗き見る。
さっきまで王子の手に握られていたガラスの塊は、今はその手を離れて寝台の端で白いシーツの波の間に転がされていた。
「エド・・・・・・どうだった?僕がガラス棒と同じものの持ち主だと確信できた?」
アルフォンスが悪戯っぽくそう問いかける。
エドワードは少しだけ上体を起こすと腕を伸ばしてアルフォンスの首を捕まえるなり、ぐいと自分の身体ごとそちらの方へ向き直った。
「馬鹿な!この俺がお前のものを見間違えるわけがないだろう!!・・・・・・アル、もっとくれよ。もっとだ。唇も、体温も、その熱い滾りも、お前の心も、人生も全てだ、お前の全てを俺に寄越せっ!!」
アルフォンスは自らの台詞で少しだけ赤く染まったエドワードの頬に両手を添えると、唇を軽く触れ合わせ、また角度を変えては触れを繰り返しながら、掠れ気味の声で問う。
「いいんだね、エド?貴方にそう言われたら、僕はもう何も遠慮はしないし、手加減もしないよ?あなたの全ても僕のものだ。」
金色の瞳に熱と欲を混ぜ込んだ視線を二人は熱く絡ませて、唇を合わせるとお互い更に貪欲に貪りつく。
隙間がないくらい素肌を密着させお互いを絡ませながら、アルフォンスの指先はそっとエドワードの尻の奥へと伸びてゆき、ゆるゆると入り口をなぞった。
*ピンクテキストの錬金術師さん*
「アアア・・・・・ッ!」
あの初めて逢った夜と同じ・・・・いや、それ以上に熱をはらんだその蕾は、いかにも物欲しげに僕の指先を迎え入れようと淫らに蠢いた。
ふと・・・・・・・・ほんの思いつきでまったく確信はなかったが、僕は早くも身悶えして息も途切れ途切れな様子の彼の耳許にそっと囁いた。
「エド・・・・まだ少し触れただけなのに、こんなになってる。あの夜に初めて触れた貴方の蕾はまだ少しも綻んではいなかったのに・・・・・・それは、何故?もしかして、あの僕の分身を象ったガラスで自分を慰めたりしたの・・・・・?」
そう言いながら差し出した卑猥な形状のガラス棒から目を背けた王子は、途端にその美貌を朱に染め、摘みたてのチェリーのような唇を噛んでいる。
「エド・・・・・・?」
さらに僕が声をかければ、途方に暮れた、なんとも頼りなげな表情で顔を上げ訴えた。
「だって・・・・・だって、分かんねぇんだよ!こんな気持ちになるのなんて生まれて初めてで、自分が何が欲しくて、何をどうしたいのか・・・・・全然・・・・・分からねぇんだよ!アル・・・お前が去ってから、ずっとずっと身体中が熱くてどうしようもなかった。これはお前が盛った媚薬の所為か?それで、俺はまるで発情期の豚みたいにただお前と交尾がしたいだけなのか?だからこんなに形振り構わずお前を探していたのか?こんなガラスのニセモノなんかじゃなく・・・・・・本当の、生身のお前を・・・・・」
その言葉を聞いた瞬間の僕の気持ちは、とても言葉では言い表せるものではなかった。
あまりにも純粋で色恋に無知な王子は、またそれだけにその告白の言葉までもが赤裸々だった。
僕がこの城から去ったあの夜から、ずっと身も心も僕を求めていたというのだ。そして、僕を想って熱を持った身体を、自らこのガラスの張り形で夜な夜な慰めていた・・・・・・?
嬉しさと同時に、黒い衝動がどこからともなく湧き上がる。これは、嫉妬か?彼の中にいる、自分自身への。
「エド・・・・・・・どうやってやったの?貴方の想像の中の僕は、どんなふうにして貴方を抱いたの?ホンモノの僕がまだ貴方を抱いていないというのに、あんまりだ。さあ、全て洗いざらい白状してもらうよ」
「違・・・・・・・・・ッ!やってねぇ!そんなコト・・・・・・・・ウアっ!?」
首を振って慌てて後ずさる彼の細い足首を掴んで引き戻し、少し強引に引き倒してその白磁のような肢体を絹のシーツに押さえつけた。
寝台が、ギシリ、とひときわ大きな音を立てた。
天蓋から垂れ下がる煌びやかな刺繍が施された薄布は途中から縄状へと魔法で形を変えられ、その先には透き通るような白く滑らかな両足が膝裏をすくうようにして括りつけられていた。
腰を少し浮かし気味にして、その下にはやわらかな枕が挟みこまれて居る為、王子は否が応でも此方に向けて大きく足を拡げ秘所をさらけ出す恰好だ。
「まだ夜は始まったばかり。時間ならたんとある。エド・・・・・今はそうやって意地を張っていても、すぐに自ら全てを話したくなるようにしてあげる」
寝台の脇に備え付けてある金細工の小箱を開けば、思った通り香油の瓶が入っていた。それを手に取り、王子の秘所に塗りつける。
これを用意しただろう城の者も、よもやこの香油が王子自身が受け入れる為に使われることになるとは思いも及ばないに違いない。
ただでさえ物欲しげにしていたそこは、香油を塗られた事でさらに敏感になったようで、王子は両の足で宙を蹴っては腰を揺らめかせるように身を捩った。
「ン、アアアアッ!あ、熱い・・・・ハァ、ハァ・・・・ッ」
「へぇ・・・・媚薬入りなんだ?この香油。エド、これはいよいよ意地を張っている場合じゃなくなってきたね?」
僕の言葉が聞こえているのかいないのか。王子は美しい金糸をふり乱しながらやみくもに首を打ち振り、涙を零して込み上げてくる猛烈な衝動に耐えているようだった。
僕は容赦なく、彼の人の熟れはじめた秘所に指を差し入れ、ゆるりと抜き差しを繰り返す。
「ア!ア!ア−−−−ッ!!嫌ァ・・・・ッ!と、熔ける・・・ッ熔けちまう!」
妖艶に腰を蠢かせる王子に思わず余裕を失いかけた僕が、一気に数を増やした指でぐちゅぐちゅと手荒に掻き回せば、瀕死の小動物のような悲鳴を上げて仰け反る。
「凄い・・・・エド。こんなに感じて・・・・!さあ、じゃあコレが貴方の中にどんなふうに埋め込まれるのか、まずは僕に見せて貰おうか」
「イヤァァァァーーーーーーー!!!」
その透明な切っ先を押し当てれば、更に激しく身を捩って抵抗するから、僕はようやくそこで手を止めた。
「何故?これが欲しいんじゃなかったかい?エド」
涙に濡れた頬に唇を寄せて囁けば、しゃくりあげながら幼子のような仕草で首を振る様が愛おしくて、思わず貪るように口づけた。
「ン、ンフ・・・・・・・アフ・・・・・・ンン・・・ッアル、俺」
「なあに?」
口づけから解放されると、濡れた睫毛を瞬かせながら愛しい王子はとうとう告白した。
「俺・・・・お前のを思い出して作らせたコレを・・・・一度はお前の代わりになりはしないかと思って・・・・・」
「したの?」
先を急かすように聞けば、王子は首を振り応えた。
「頑張ったけど・・・・・出来なかった・・・・・」
*らく*

*らく*
「そう、出来なかったの。・・・・・・でも、そんな素直な貴方も可愛いよ、エド。」
汗と涙で額に張り付いた金髪を手で払い上げてやりながら、僕は彼の瞼と唇にキスを落とす。
そして自分の指とガラス製のそれにも香油をたらすと、彼の秘所にもう一度塗りこみながら指を進めてゆく。
「ひあぁぁぁ・・・・・・ん、あぁぁ・・・・・・んフっ!!」
彼が腰をうねらせると、吊るされた両の膝が震えて揺れた。指を埋めたその場所はやけに熱くトロトロと蕩けて時折指を締め付けてくる。
「エド、僕のところから良く見えるよ。ほら、ここがこんなにグチャグチャに柔らかくなってるのが。こんなになっているんだから、これくらい簡単に入ってしまうよ?」
アルフォンスは指をその場所から引き抜くと、香油でぬめらせたガラスの先端部分を押し付ける。冷んやりとして硬質なその感触にエドワードは思わず脚を閉じようとするもままならない。
「いやああ・・・・・・ああ・・・・・・」
尚も頭を左右に振るエドワードの手をアルフォンスは空いている方の手で取ると、ゆっくりとそのガラス棒へと導く。その意図に気付き、王子は更にかぶりを振る。
「いや・・・だ・・・・・・いやだ・・・っ」
「大丈夫だよ。僕が一緒に手伝ってあげるから、自分で握ってごらん?」
優しくて熱くてどこか有無を言わさぬ響きを持った声で、アルフォンスはエドワードにそれを握らせると、その上から自分の指も重ねる。
そしてアルフォンスが軽く力を加えると、ガラスの先端は簡単にエドワードの秘所の入り口に入り込んでいった。
「ああああああ・・・・・・んん・・・・・・ああっ!!」
媚薬で完全に溶かされていたエドワードのそこは、何の抵抗もなくズブズブとそれを飲み込んでゆく。
あっという間に最奥までガラス製の模倣品は埋め込まれ、最初は無機質な温度だったものは、すぐに人肌にしても熱い位の温度に馴染んだ。
「ほらね、全部入ってしまったよ、エド。さあ、後は自分でやってごらん。一人でできるよね?」
添えられていたアルフォンスの指が離された。自分でやれという、その恥辱に顔を真っ赤に火照らす。
しかし身体の底から湧き上がる貪欲さには抗えない、促されるままに自らの手でそのガラス棒の抜き差しを始めれば、その快感に支配されていつしか一心不乱にその行為に没頭した。
「ンンッ!!・・・はぁっ!・・・あ、あ、あふっ・・・・・・っ!!」
脚を吊るされて開かされ、丸見えになった秘部に自らの手でガラスの異物を出し入れして息を乱すエドワードの痴態を目の前にして、アルフォンスもゴクリと咽を鳴らす。
自分の張り詰めて勃ち上がるこれで、今すぐ突き上げてしまいたい。沸き起こる衝動を止めるのに精一杯だ。
その欲望を何とか抑え込み、彼の立ち上がっている中心に指を絡めて更なる快感を与えようとしたところ、息を乱しつつも途切れ途切れにエドワードが訴えてきた。
「ア、アルッ・・・・・・いや、だ・・・これじゃ、いやっ、アル・・・アルのが・・・欲しっ・・・」
*ピンクテキストの錬金術師さん*

*みなもさん*
搾り出すような声は欲に掠れ、目尻から零れる涙がシーツへと消える。
汗ばむ肢体に解けた髪が張り付き、大きく仰ぐ胸では、王子の健気な突起が、紅く固い木の実のように張り詰めている。アルフォンスの掌の中にある、先程愛しんだエドワードの情は熱く脈打ち、解放の時を待っていた。
誰の目にも、エドワードが限界であることは確かであった。
「アル、…アル、あ、ア、る」
言葉を失ってしまったかのように、我が名前だけを切なげに呼ぶ唇。吐き出す呼吸と共に熟れた舌が零れ、乾くのかしきりに舐める。その様も、なんと魅惑的か。
エドワードの手に握られたガラスのそれは、アルフォンスの目の前で、アルフォンスを模したニセモノであるにも関わらず、まだ叶わぬ彼の中に我が物顔にあった。そんなにも、と思うほど深く埋められたかと思えば、今にも抜けそうなほど浅くなり、そしてまた、深く限界まで、エドワードの中に消えていく。
「中が真っ赤だ。とてもよく見える。」
職人は果たして、王子の中に埋められることを想定して仕上げたかはわからないが、王室への献上品だ。美しく純度の高いガラスで作られたそれは、押し開かれたエドワードの体内を惜しげもなく透かし、アルフォンスへ晒していた。まさに魅入られるとはこういうことを言うのだろう、目が離せない。
「お前、は、…ひど、い、奴だ。」
エドワードの瞳から大粒の涙が溢れたかと思うと、唇を噛み締めて、アルフォンスから顔を背けた。
自身に絡めていたアルフォンスの掌を弾き、自ら指を這わせる。
ガラスのそれを握りなおし、ゆったりとした動きであったのを改め、動きを早めた。
最初からこうすればよかった。身体の熱が引いてしまえば、この気持ちごと晴れるだろう。
愛を語るくせに、与えようとはせず、やっとこうして心を開き、肌を重ねているというのに、やはり雲を掴むように擦り抜ける。
あの日も、自分を置き去りにして消えてしまったではないか。
なんという屈辱だ。
ベッドの天蓋に吊らされた足を強張らせ、呼吸を詰める。
疎かになりがちな自身を慰める手を濡らしながら、覚えたての悦を追う。
エドワードの意図を知り、その腕を、シーツへと縫い付けて、アルフォンスは閉じることのできない足の間に身を滑らせた。
目の前が染まる程の怒りで、エドワードは声を上げた。
「どけ!!お前など、いらぬわ!出て行け!ここから消え失せろ!!」
捕らえられた腕を振りほどこうと暴れる頬に口付ける。噛み付くような素振りを見せるその人の、体内に埋め込まれたままの作り物を、今度はアルフォンスが掴んだ。
ゆっくりと引き抜いていく。
「は、んんっ!」
少しの衝撃でも爆ぜるまでに高まった身体を、半ば意地だけで留める。
溶けた香油が絡んだそれが、傍らに転がった。
初めて体内に受け入れた物とは比べようもない熱い猛りが、押し当てられる。
「少し、嫉妬をした。だから、すこし意地悪をしたくなったんだ。」
アルフォンスの唇が、瞼に落ち、目頭に溜まっていた涙を吸った。
鼻先を掠め、唇の端に口づけられる。
上唇を吸われ、下唇に舌が這わされて、拒みきれないままに、咥内にそれを許してしまった。
「お前は、勝手だ。」
シーツに迷う腕を首に絡ませるよう導くと、アルフォンスの短く整えられた髪の中に指を差込み、エドワードがしがみついてくる。
「貴方を、僕だけのものにしたい。この瞬間だけでも」
*水渡つぐむさん*

*染さん*
「この瞬間だけ?本当にお前はそれでいいのか?」
熱に浮かされたような熱い視線を投げかけた王子は、僕の頭を抱き抱えた指の先に髪を絡めながらやるせない様子でそれをかき乱した。
「エド・・・・・」
獲物を狙う猫科の動物の表情で僕の下唇をさっきのお返しとばかりにペロリと舐め上げると、愛しい王子はとうとう僕の心にとどめを刺した。
「俺は『瞬間』なんかじゃ足りねぇ・・・・・・今この瞬間から死ぬまでずっと、お前の全てを俺だけのものにできないなら、いっそ始めから何もいらねぇ。だからアルフォンス、お前の全てを俺に捧げろ。そうしたら俺も、ひとつ残らずお前に自分をやってもいい」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・!」
不覚にも、声さえ出すことが出来なかった。
−−−−−−−−まさかこの僕が。
この世のありとあらゆる色恋を経験したと思っていたこの僕が、よもやこの初心な王子に遅れをとるなんて・・・・!!
しかし、そうではないのだ。きっと僕はこれまで本当の愛を知らずにいながら、知りつくしたつもりでいたにすぎなかったのだ。この目の前の人こそが、本当の愛を知っていた。そして、それを僕に教えてくれた。
一度合わせた両掌を王子の足に絡まっている紐にあて元の薄布へと戻せば、王子の足はしどけなくシーツの上へと落ちた。僕はその片方を恭しく引き寄せ、足の甲に口づけをした。
「エドワード・・・・・僕にとって、貴方は『王子』ではない。僕に全てを与えてくれる『神』だ。喜んで、僕の全てを貴方に捧げます」
目をあげれば、そこには花のように笑う王子がいた。
「よくぞ言ったアルフォンス。良い覚悟だ。それでこそこの俺が見込んだ男だ。約束どおり、今から俺の全てをお前に与えてやる・・・・・さあ、いかようにもお前の好きにするがいい」
尊大に言い放った王子は、そのまま再びシーツへと肢体を投げ出した。けれど何故か視線を宙にさまよわせ、薄らと頬を赤く染めている。さっきまで、散々あられもない姿を見せてくれたというのに、この人はまったく慣れるという事をしないようだった。
僕の胸に愛おしさが溢れる。
このまだ開きかけたばかりの美しく気高い薔薇を手折ることなく大事に慈しみたいと、心の底からそう思った。
まだ開きかけたばかりだというのに手酷く扱ってしまった蕾に指を這わせれば、幸いにも案じていた傷はないようだった。そればかりか、既に蕾はしとどに濡れそぼり、そこを満たす何かを待ち望んでいるかのようで、はしたなくも僕の喉がゴクリと音を立てる。
先程までの奔放に快楽を追う姿とは一変して、すっかり大人しくなってしまった人を怖がらせないようにそっと覆いかぶさると、誓いの意味を込めて、ゆっくりと口づけた。すると、程なくして彼の唇の隙間からオズオズと可愛い舌先が忍び出して僕の唇やその裏側、果てには咥内までを愛撫し始める。その震える顎と舌先に、彼が無理をしていることが痛いほどに分かる。
その彼本来の姿を垣間見た僕は、自分はなんという辱めをこの人に強いてしまったのだろうかと、改めて先程の行いを悔いた。
「エドワード・・・・・こんな酷い男に、無防備にも全てを許してしまうなんて・・・・・・・・・・・・・!僕は、そんな向う見ずな貴方が心配だ。貴方のお陰で、こんな穢れた僕でさえこの先を身綺麗に生きていかなくてはと決意してしまった」
食いしばった歯の間から漏らした僕の言葉に、王子は緊張をにじませながらも嬉しそうに笑った。
「アル・・・・過去の事は全て忘れろ。お前は、俺だけを覚えていればいい・・・・・・・」
そして口ごもり、暫くの逡巡の後、再び口を開いた。不自然な程、神妙な口調だった。
「これからは、なにかと言い訳をつけて後回しにしていた閨でのたしなみについてもしっかり学ぶようにする。お前に世界一の快感を与えてやれるように出来る限り尽力する・・・・・・・だからアル!・・・どうか、今夜のことで全てを決めつけないで欲しい」
今までの尊大な様子を一変させ、まるで縋るように言う王子の様子に、僕は息を飲み、そして・・・・・・胸にどうしようもない痛みを覚えた。
*らく*
エドワードの顔をてのひらで包み込み、アルフォンスはあらためて近づいた。
クリスタルよりも透き通ってきらめく涙の粒を唇で吸い取る。そのまま白い頬を寄せ、触れ合わせるだけの口付けを与えてから、ひたと視線をあわせた。
「……最初に戻るよ。……あなたが欲しい。手にいれたい」
そっとアルフォンスは囁いた。
「俺こそ、お前が欲しい」
エドワードは腕を回した。
二人はそのまま見つめあい、体を寄せた。エドワードは足を開いて。アルフォンスは腕の中に王子の体をすくい取って。ひくひくと愛を受け入れるために潤み、震えているそこが、アルフォンス自身にひたりと吸いついた。
「ゆ……っくり」
「かしこまりました」
アルフォンスはゆるりと微笑み、体をすすめた。熟れきった肉が、花がほころぶように開かれていく。エドワードはあえいだ。
「おま……え」
「……はい」
「お……っき…………ぃ―――あっあ……」
エドワードはのけぞり、そのまま声を失った。ガラスのそれよりはるかに大きく、硬い質量が、ゆっくりとエドワードを甘く引き裂いていく。
「あつい……」
「王子、あなたの方が熱い」
アルフォンスもはあ、と肩で大きく息をついた。まるで息をするように波うつ濡れた肉が、自分を飲み込みながら締め上げてくる。エドワードは体のすすめるたび、あ、あ、と小さく声を零した。そして、完全にひとつになったときに大きく息をついた。ゆるゆると微笑をこぼしながら。
*KKさん*
腕の中にいる王子が辛そうに時折息を詰めながらも浮かべたその笑顔に胸を撃ち抜かれた僕は、思わずため息とともに声を上げた。
「・・・・なんて顔をするんだ、エド・・・・・・!ああ・・・愛おし過ぎて、どうかしてしまいそうだ・・・・!」
同時にせり上がってくる凶暴とも言える衝動を何とかやり過ごそうと、ギリと奥歯を噛みしめる。愛しい人の中に埋め込まれた自身が、これまでになく更に熱く滾り張りつめていくのが分かる。王子もまた僕の怒張が勢いを増していく様をつぶさに感じとったらしく、小さな悲鳴を上げては切なげに背を反らした。
「ア・・・・・ッ!・・・・・・・ウソだ・・・こ、んな・・・・・・また、大きくな・・・・・・アアッ!」
「貴方があまりにも素敵だから・・・・・ッ・・・これは僕の一存ではどうにもならない・・・・・でも、ゴメンね。辛いよね・・・・・・エド」
全身をわなわなと震わせて耐える姿が健気で、その汗ばむこめかみに唇を寄せながら呟く僕の額にもまた、次々と玉のような汗の粒が浮かび上がっては下へと滑り落ちて行った。
ここで、不用意に動く訳にはいかない。限界までに拡げられた皮膚の薄い柔襞は、少しの動きで傷ついてしまうに違いなかった。彼が無理なく受け入れられる状態になるまで何とか耐え、ふたりで共に高みを目指したい。
激しく突き上げてしまいたいという雄の本能を噛み殺しながら耐える僕の下では、王子が同じく眉根を寄せて、フ、フ、と小さく息を吐いてはどうにか力を抜こうと頑張っている。その様子を見るだけで、ますます自身に熱が集まってしまい、状況は更に悪化した。
「ア・・・・・・ヒ・・・・・・・ッ!イヤぁ・・・・・・っ!そんな・・・・・どこまで、大きく・・・・・・ウア・・・」
膨張すればすなわちそれは自らをより圧迫させることになる訳で、いよいよ苦しくなった僕は彼の身体を壊してしまうと危機感を抱き、ここは仕切り直した方がいいだろうと腰を引いた。
しかし。
「エド・・・・ッウ・・・・・・ク・・・・・やめ・・・・・!」
身体が離れて行くのを、彼の両脚が僕の腰に絡み阻止してしまったのだ。そればかりか、更に奥まで咥え込もうと強く腰を押しつけてきた。
「――――――――ッ!!」
声にならない悲鳴を上げながら仰け反り、シーツの上で悶絶する細い身体の美しさに、目眩さえ覚えた。動く事も出来ず。かといって身を引くことも赦されず。苦痛を伴う甘い愉悦に息も絶え絶えの僕を、またあの挑戦的な瞳が見上げてきた。
「赦さぬ。一度その自身で・・・俺の身を穿ったのならば・・・・・・・ク・・・・・・その、子種を注ぐまでッ・・・・・逃げる事は赦さん・・・・ッ!」
瞬間、視界が赤く染まった。
*らく*
「ひぃ・・・・・・あああぁぁ!!!」
彼の中でまた大きく硬くなると、エドワードの悲鳴とも狂喜とも知れない叫びが響きわたった。
アルフォンスは、その白い身体の上に覆い被さり頭の中が真っ赤に染まりながらも、ただひたすらに暴走してしまいそうな衝動を耐えてやり過ごす。
この国の全ての民から慕われるエドワード王子。先日も水害と汚れた水による病気の発生を訴えにきた貧しい民の直訴を聞き入れて、すぐに街の治水工事を行い、広場に清潔な水の湧く噴水までも作らせたと聞いた。
そんな賢く高潔の誉れ高い王子が今、自分の腕の中にいる。
金の髪をシーツに散らし頬を上気させ、口からは掠れた声にもならない声を洩らし、眉根を寄せて閉じた睫毛をぴくぴくと震わせている。なんと壮絶な色香だろう。
そして今、自分の中心は彼の奥深くで繋がっている、その愛おしい人の中は逃さないとばかりに熱く潤んできつい位に締め上げてくる。
アルフォンスもその締め付けに眉間を寄せると、そこに汗が伝ってエドワードの頬に落ちた。
吸い寄せられるように、その頬に唇を這わせて再び唇を重ねようとアルフォンスが身じろぎした途端、今までとは明らかに色の違う喘ぎ声がエドワードから発せられた。
「ああああ・・・んん!!あ・・・なに・・・?!ふっ・・・・・・っく!!ああぁぁん!!」
王子の嬌声と共に、腰に絡んだ脚がブルブルと短く痙攣しながら、勃ちあがったその彼自身からは薄っすらと白いものが押し出されるように吐き出された。
「な・・・なんだ、いまの・・・ああっあっ!ひァァァ・・・・・・ン!!!」
「ここが貴方の感じるところなんだね?」
あまり大きくは動かずに、しかしその場所を的確に捕らえて小さく何度も擦り上げると、更に王子は高い声で啼く。
「ひゃあ・・・・・・あ、あ、あ、アルッ!ああ!ダメだぁ!!そっ、そこは・・・ああッ!!ビリビリするっ!うぁん!!」
叫ぶ王子の唇を啄ばむようにしながらも念入りにそこを攻め続ければ、王子の秘部は徐々に潤いを増してきて、いくらかスムーズな動きが取れるようになった。
その様子を窺いながら、少しずつ腰の動きを大きくしてゆく。そして愛しい王子の耳元に腰が砕ける程の低音でアルフォンスは囁いた。
「ああ、僕のエドワード・・・・・・愛してる・・・お言葉通り、貴方の中に僕の子種もこの想いも何もかもを注ぎ込むよ・・・・・・僕のものであなたを一杯にしてしまおう・・・。」
王子はそんな不埒なアルフォンスの言葉に、ただ腰を震わせながら、掠れた喘ぎ声を洩らすだけだった。
*ピンクテキストの錬金術師さん*
彼の身体の感じる場所を探り当てた途端、その人の白い素肌が朱に色を変えた。
「アッアッアッア・・・・・・ッ!そ・・・そんな、動かな・・・・・ア!」
ビクリビクリと全身を痙攣させ、僕の一挙手一投足、果ては僅かに息を詰めるのにさえつぶさに反応し、悲鳴にも似た嬌声をあげるその様の、何と狂おしく色めいた事だろうか。殆ど本能のみに任せて激しく腰を打ちつけながらも、僕の全神経は彼の人の艶姿にひたすら向けられていた。
薄く織られた光沢ある絹布の波に模様を描きながら泳ぐ、美しく筋肉のついた細めの手足。
逸らされる首筋の艶めかしさ。布の上に広がっては乱れる金の髪。
忙しなく上下する胸の先端に飾られている、輝石にも似たふたつの果実。そして・・・・・・・。
絶え間なく白濁を散らしている、彼の人の熱い分身。
それなりである、僕が暮らす屋敷よりも更に高く、無数に灯された蜀台の灯りも届かない程高い天井に、愛しい人の切ない喘ぎと声がこだまする。
先程までは気持ちばかりで思うようにいかなかった僕だけの愛すべき蕾はすっかり綻び、今では思う様、僕の熱い肉を貪欲に貪っている。忙しなく収縮を繰り返すそれは、まるで咀嚼している動きにも似て、うっかり気を抜けば眩暈を起こさせる程に恐るべき甘美な波を断続的に仕掛けてくる。
今まで感じたことのない快感と、そして苦痛。
それらによリもたらされるものは、おそらく人が正気を保っているには限界ぎりぎりの快感だった。
互いの身体を、まるで魔物のように容赦なく貪る僕とそして・・・・・・高貴な魂を持つ人。
この背徳的で倒錯的な状況を、第三者の目線から冷静に見ている自分がいたのだが、如何せん、その冷静であるはずの自制心までもがいつしか彼の人の艶姿に捕らわれてしまい・・・・・・・。
その先はもはや、語るべくもない。
片田舎の落ちぶれた貴族と、方や国中の民から尊ばれる気高き美しい王子。そしてさらに、決して子を成すことなど無い、性的に同一の属性を持つ者同士。
互いの想いを通じ合わせる以前に、僕と彼の愛には障害となる事柄があまりにも多かった。
けれど、それさえもが今の僕たちにとっては、加燃剤にしかなりえなかった。
*らく*
アルフォンスとエドワード王子は、二人の汗と幾度も吐き出され続ける王子の白濁の体液とで、身体のあちこちを濡らしてぬめらせながらも、上に乗るアルフォンスの律動は飽くことなく続いている。
善いポイントを細かく小さく擦りあげたかと思えば、次にはギリギリまで引き抜いて一気に最奥まで打ち付ける。
その度にエドワードから歓喜の悲鳴が上がり、繋がる部分をきつく締め付けられればアルフォンスも小さく呻く。
「ふっ・・・っく・・・ああ!そんなっ・・・アルっ!!お、お前・・・すごっ・・・過ぎ、るっ!!」
「っく・・・・・・エドっ!!そんなに締め付けないでっ!!」
「そっそんなこと・・・・・・ああああっ!!!」
顎を仰け反らせて、王子はもう何度目かも分からない絶頂を迎える。アルフォンスはその快感に身を任せて腰を突っ張り断続的にヒクつく腰を抱え直すと、更に深く自身を蕾に埋め込む。王子から、また掠れたような甘い悲鳴が洩れた。
愛おしい、愛おしい。この存在の全てが。こうやって身体を繋げた先から溶け合って混ざり合ってしまえばいいのに。
自分達はこれからどうなるのだろう。もう、この王子を自分が手放すことなど出来るわけがない。そして、エドワードが同じく自分を欲してくれているも嘘偽りのない本心だと分かっている。
この腕の中の輝くほどに美しい高貴な人を、名実ともに生涯に渡って手に入れるにはどうすればいいのだろうか。
アルフォンスは腰を送りつつ眉を寄せて、可愛い啼き声を横に聞きながら思い巡らす。
一国の王子という身分とか同じ性を持つ者同士だとか、それらの問題を己の知恵と力で乗り越えて、僕はこの人の全てを手に入れてみせる。
「あっ、あっ、あっ・・・・・・んん・・・イっ・・・アル!!」
「っエド・・・・・・イイんだね?イキそう?僕に教えて・・・・・・」
「うあ・・・あっ・・・いぃ・・・いいっ!うっ、アル・・・俺もうっっ!!」
何度も頷きながら素直にその快感を訴えてくる彼の痴態に、また胸が凶暴な程の甘い衝動に見舞われて、半ば無我夢中で動きを早める。
王子の蕾は今は滑らかに水気を孕んで、咥え込んだ熱棒を出し入れする度に忙しなくいやらしい音をたて、それに更に煽られた。
「あっ、あっ、アル・・・ちゃんとっ!ちゃんと俺の中にお前の・・・っ、お前の全てをっ!!・・・あああああああぁぁぁ!!!」
「--------っ!!!」
エドワードが最後に大きく絶頂を迎えると同時に、アルフォンスも搾り取られる様にその想いの全てを中へと注ぎ込んだ。
白濁にまみれ、浅く息をつきながら、弛緩したようにその四肢をぐったりと投げ出して放心している王子の姿は、それでも尚も神々しい程の高潔さを保っていた。
アルフォンスは指先でエドワードの顔に汗で張り付いている金髪を払ってやる。指が触れると閉じていた瞼が開かれて、琥珀のような深い金色で見つめられると、アルフォンスの胸がまたドキリと鳴る。
二人はそのまましばらく見つめあった後、無言の約束でも交わすかのように、ゆっくりと再び深く唇を重ね合わせた。
*ピンクテキストの錬金術師さん*
あの夢のような日から、もう10日が経ってしまった。
僕はまた、かつての栄華などすっかり消え失せた大きいだけのうらびれた屋敷で、静かな日々を送っていた。ただ以前と違うのは、身に纏う服が女物ではなく王族にしか許されていないはずの男子用の装いである事。そして、横柄な態度で僕を奴隷のように扱っていた義母や義姉たちの態度が一変して、見ているこちらが哀れになるほどおどおどと媚びへつらう様になっていた事だ。
あの日、身も心も焼くような熱い愛の契りを結んだ僕とエドワードは、互いだけを生涯の伴侶とする許しを得るべく王と王妃の許へ参じた。しかし当然のことながら、たった一人の我が子である王子からのまさかの申し出に、王妃は卒倒し、王は鬼のように怒り狂い、また控えていた大臣達も、『王子が乱心した』『すわ一大事』などと騒ぎ立てる始末。
すったもんだの末、10日後に議会を召集して王子と僕の婚姻を認めるかどうかを決めるという話に落ち着きはしたが、エドワードはその後僕が城に留まることを良しとしなかった。
たったひとりで矢面に立たせることなど出来ないと言い募る僕に、エドワードは茶目っ気タップリに片目を瞑って見せながらこう言った。
「俺にはとっておきの最終兵器があるんだが、それを使うトコをお前に見られるのはカッコ悪いからイヤだ。だからお前はいっぺん実家に帰ってろ。心配すんな。必ず迎えに行ってやるから、お前は日がな一日俺のことだけを考えていい子で待ってろ」
いっぱしの色男のような科白を吐くけれど、つい先ほどまで寝所で可愛い鳴き声を聞かせてくれたのはこの人の方だったのだ。そんなギャップさえこの上なく愛おしく思わず目を細めてしまった僕と、同じく蕩けるような笑顔を浮かべた彼は、『約束のキス』というにはあまりにも長くそして甘いキスを交わして別れたのだった。
その『約束の日』である今日。会議は昼から開かれると聞いていたが、今はもう夜更けだ。彼は今頃僕を迎えに此方に向かっているのだろうか・・・・・それとも。気がふれたと思われ、無理やりどこかに閉じ込められてしまっているなどということはないだろうか。
そんな不安に駆られ始めた頃、屋敷を訪れる者があった。エドワードが幼い頃から教育や身の回りの世話などをしていたという、爺やのフーだった。爺やは息せき切って屋敷に飛び込むなり、夜中の訪問の詫びもそこそこに僕に取りすがってきた。
「後生でございます!今すぐわたくしめと一緒に城へお戻りください!王子が・・・・王子が・・・・・!!」
「エドワードがどうしたんです!?」
そのただならぬ様子にエドワードの身に何かが起きたのだと思った僕は、爺やを伴い城へと向かうべく外へ飛び出した。
しかし、そこにある爺やの乗ってきたと見られる馬車はあまりにもアンティークで、それを引く馬までもが『爺や』だった。これではいつになったら城へ辿りつけるのか分からない。僕は合わせた両手を馬とそして馬車へとあて変化させた。
現れた二人乗りのオートモービル(ターボ付き)に爺やと乗り込み、とりあえず子猫に変身させた馬だったものを目を白黒させながらナビシートに納まった爺やに手渡し急発進させる。
「あ・・・・・あ・・・・アナタ様はまさか・・・・・、魔法使いなので・・・・!?」
「魔法使い・・・・まあ、魔法を使う人間をそう呼ぶのならば確かにそうですね。さぞ便利だろうと趣味で習得したものの、人から便利に使われるのはまっぴらなので、これが使えることは秘密なんですけど」
大袈裟に声を上ずらせながら言う爺やの様子を妙に思いながらも、僕は一刻も早く城へとたどり着かなければと気のない返事を返した。けれど爺やは爺やで一人勝手に盛り上がり、まくし立てるような勢いで昔語りを始めた。しかしその内容が僕の耳に入ってくることはなかった。
まさしく飛ぶような勢いで(実際速度が出すぎて何度か離陸しかけた)辿りついた城は、夜中だというのにまるで昼間のような賑わいだった。至る所に灯りが掲げられ、たくさんの人間が忙しなく行き交い、大声を上げている。一体どうしたことだろう。
不思議に思いながら爺やとオートモービルから降り立った僕を見るなり、その大勢の人間達は一斉に一歩下がって頭を下げた。
「皆の衆、ここにおわすお方こそ、我らが王子エドワード様のお妃となられるお方ですぞ。やはり、エドワード様は道を違えてはなかった!このお方こそ、エドワード様のお妃となるべくしてこの世にお生まれになった方!」
戸惑う僕の後ろから爺やが声高らかに宣言すれば、人々はザワザワと声をあげ爺やに何事かを尋ねている。
「そうじゃ、その通り!このお方は、もはや廃れてしまった古の業である『魔法』を見事復活された魔法使いだったのじゃ!エドワード様がお生まれになった時に占い師が予言したとおりじゃ!『この光輝く王子が魔術を行使する者を伴侶とすればこの国には必ず永き平安が訪れる』と。これでこの国は安泰じゃ!めでたい!」
その一言で一気に周囲は沸き、その歓声は次第に城中へと伝播していく。僕の周囲にいる人たちはさらに頭を低くし、石の床にひれ伏す者まで現れた。
---暇つぶしに、館の地下の書庫から引っ張り出した古文書片手に遊び半分で習得した魔法が、まさかこんな場面で役に立とうとは思わなかった僕だ。
一方、幾重にも周囲を取り巻く人の波に、前に進むこともままならない僕は気がせいていた。一刻も早くエドワードのもとへ行きたいのに・・・!
と、そこへかすかに愛しい声が聞こえたような気がして、ふと顔を上げた。
「アル――――ッ!」
城の外壁の高い位置にある石造りのバルコニーに、絹のドレスシャツを羽織った愛しい人の姿があった。良かった。ひとまず無事なようだった。けれど、早くその身体を抱き締めて無事を確かめたかった僕は、一度合わせた両手をエドワードへと向け広げた。
「エドワード、おいで!」
周囲の者たちは一瞬にして息を飲んだが、エドワードはふわりと笑うと、ためらうことなくバルコニーの柵から飛び降りた。両手をエドワードの方へと向け、周囲の風の力で落ちてくるエドワードの身体を優しく抱きとめてやりながら自分の腕の中へと運ぶ。
抱きあう僕達に、周囲から再び大きな歓声が上がった。
「アル!このせっかち野郎!たった今大臣共全員をウンと言わせたから、城の皆に婚礼の儀の準備をさせてお前を迎えに行くところだったのに!」
「エド!とても心配したんだよ!だって爺やのフーさんが・・」
僕達の直ぐ横にいた爺やは、ウンウンと頷きながらその先を引き継いだ。
「そうですぞ。まさかあのお気の強い王子が、アルフォンス様との婚姻を認めないと王や議会から反対された途端」
「爺!余計なことを申すな!」
真っ赤になってその口を塞ごうとするも、僕の腕に抱かれたままの彼にそれはかなわなかった。爺やは構わず続ける。
「あの琥珀のような瞳から大粒の涙をはらはらと流して、それはそれは哀れなようすで泣き崩れておなりに・・オオ!おいたわしや・・!」
その時の様子を想像したらしい周囲の者たちが、まるで貰い泣きでもするように溜息をつきながら涙を流す。
腕の中の人を見れば、こちらは熟れたラズベリーのように真っ赤になって、僕の胸元のタイの端を指に絡めて唇を尖らせていた。
「畜生・・・・俺の必殺技を知られたくなかったからわざわざお前を実家に帰したのに、これで意味がなくなった。大体俺が魔法使いと結婚すれば国が安泰だなんてそんなハナシ初めて聞いたぞ!?じゃあ始めからお前が魔法使いだって言ってれば事はもっとすんなりいったってワケか!?」
エドワードの最終兵器とは泣き落としのことだったらしい。だが、結局はそれも徒労に終わったようだったが。
それにしても一国の王と王妃、そして大臣やその他大勢の人々皆が、涙ひとつで全てを許してしまう程、エドワード王子のアイドルっぷりは尋常ではないのだろう。
「こんなに皆から愛されちゃってる俺を泣かせたりしたら、お前只じゃすまねぇぞ。覚悟はいいか?」
まだ腕の中に納まっている愛しい王子は、僕の首に腕を回してギリギリ唇が触れ合いそうな距離で今更な問いを投げて寄越した。
僕はにやりと笑い、その唇にちゅ、と一度だけキスをしてから言った。
「それは困ったな。毎日貴方を嬉し泣きさせるつもりでいるんだけど、これは相当の覚悟が必要だというコトだね?」
後日執り行われた成婚の儀は、歴代のどの王子よりも盛大なものであったと、アメストリス国王家の文書に記されたという。また、その後も脈々と歴史を紡いだアメストリス国の王が持つ王笏が男根を模した形状となったのは、このエドワード王子が即位してからのことだそうだ。
*らく*
|