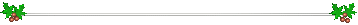 「クリスマス、か。もう」 12月に入り、赤と緑に彩られた街の風景は、クリスマスが近いことを教えてくれる。ただ、私にとっては別にどうということもない平常の中の一日。 「ツリーとか綺麗ですよね」 今日はちょっと趣向を変えて、と大先生が桜の香りがするお茶を煎れてくれた。冬に桜というのもミスマッチなような気もするけれど、こうやってストーブの前で大先生と一緒にいたら、まるで春の中にいるような気分になってくる。 「うちでは何年もやってないが、今年はパーティーでも・・・」 「誰が準備をすると思っているんですか?」 仕事が一段落ついたのか、若先生が白衣を脱ぎながら入って来た。 「もちろんおまえ」 「あのな、診療も休みじゃないし、もう今は早季子さんもいないんだし」 「そんなもの、ケーキを予約して、適当にチキンでも買ってくればいいじゃないか」 「親父がやれ親父が。ともかく俺はそんな余裕はないからな。ただでさえ患者が多いのに」 最近忙しいせいか、多少イライラしている若先生がぶっきらぼうに言い捨てる。私が言われたわけでもないのに、なぜだか胸がチクンと痛む。 クリスマスなんて普通の日、そう自分に言い聞かせる。 慌ただしく出ていった若先生の背中に、大先生が特大のため息を浴びせかけている。その子供っぽい仕種に、思わずクスリと笑みがこぼれてしまう。 こんなにもここは暖かく、これ以上望むことはしてはいけないはずなのに、何かがちょっと悲しく思えるのは、街の雰囲気のせいだろうか。 家での状態は相変わらずで、一人きりで冷えきった部屋は私を拒否しているようでますます気分が滅入っていく。適当に夕食を済ませ、何も考えないでいいように勉強に集中する。将来私も受験生になる。兄が行った学校でなくては進学させないと言った母は、たぶん本当にそうするだろう。私に選択肢は残されていない。それから先はなんとな行きづらくなってしまい、若先生のところへは行けないでいる。少しだけあの場所に依存してしまったことを後悔する。優しい手も優しい言葉も、私のものではないのに、何を勘違いしていたのだろう。あそこへ行くようになってから、何度も思ったこと。繰り返してはいけないのに、繰り返してしまう。 イブだからといって、私の生活は変らない。とりあえず通知表を受け取ったぐらいだろうか。クラスメート達はパーティーだとか騒いではいるけれど、取り立てて親しくしていない私には関係のない話だ。 いつもより早い時間に帰宅すると、大先生が玄関先で待ち構えていた。 「香織ちゃん、デート」 ニヤリとした先生が悪戯を成功させた子供のような表情を浮かべている。 「まあまあ、これでも」 渡された紙袋の中には見たこともないようなかわいらしい洋服が入っていた。 「あの、これ」 「クリスマスプレゼント」 生まれてから今まで聞いたことがない言葉に一瞬言葉を失ってしまう。 「ダメです、先生。受け取れません」 「なんで?」 「なんでって、もらう資格なんてないです」 「資格?資格ってなんじゃ?わしがあげたいからあげる。それ以上の意味はないぞ」 「でも!!」 それでも、こんなことをしてもられる立場にないことは自分自信が一番よくわかっている。だからこそ、どうしていいかわからなくて大先生の好意そのものを無碍にすると分かってはいても拒否してしまう。 「香織ちゃん、これはわしがしたいからやっているだけだから、子供は黙って受け取ればいいの」 「大先生」 紙袋をもったまま、俯いてしまった私に、大先生の楽し気な声がかかる。 「まあまあ、これに着替えて」 「え?ええ???」 背中を押されて、取りあえず自分の家へと入る。 「ここでまってるから、五分ね」 「ええええ???」 よくわからないままに、大先生の勢いに乗せられて、自室へと着替えに戻る。 はてなに囲まれながら、とりあえず着替えてみる。こんなにも女の子らしい洋服は制服以外では初めてで、妙に落ち着かない。 「あの、先生」 その姿を見せる勇気はなかったけれど、区切られた時間設定に慌てて大先生の元へと駆け寄る。 「うん、思った通りかわいいかわいい」 「え?え?えーーーー?」 「香織ちゃんはかわいいんだから、もっとそういう格好をすればいいのに」 女の子の格好をする私を汚いモノでも見るかのように見下す母親の顔を思い出して、複雑な感情に捕われる。あの人は、私が女性らしいことをすることをことごとく嫌うから。 「さ、お嬢さんお手をどうぞ」 そう大先生に促されて、エスコートされる、というのだろうか、なんか私にあまりに不釣り合いでどうしていいかわからない。 そのまま引きずられるようにして大先生に連れていかれたのは、当たり前と言うか、もちろん大先生の家。職場ではなくて裏側にある居住部分には夕食を食べに何度も来たことがある。ここ最近は近寄っていなかったけど。 「料理ができないから、ケータリングで悪いけど」 いつものリビングに、小さなツリーが飾られて、なんとなくクリスマスっぽくなっている。テーブルには骨付きチキンや見たことがないごちそうが並んでいる。 「香織ちゃんとパーティーがしたくて」 そう言われても、よくわからなくて、呆然としてしまう。 ぽんぽんと頭を撫でられて、ようやく現実に戻る。 「香織ちゃん?」 いつのまにか涙を流していた私を心配そうに大先生が覗き込む。 目にゴミが入ったふりをして、笑顔を作る。 こんなにも暖かい場所にこの日この瞬間私がいられるだなんて。奥からどんどん沸き上がってくる涙を堪えながら、大先生がよそってくれた料理を口にする。 「ありがとう、ございます」 やっと搾りだせた言葉は何の変哲もないただの感謝の言葉でしかなくて、それ以上何も言えない私をそれでも暖かく見守ってくれる。 「これはなんだ?」 疲れ切った顔で入ってきた若先生は、さも不機嫌そうに口を開いた。 「ぱーちー」 大先生は大先生で、さらに煽るようにバカにしたようなアクセントで受ける。 「ああ、そうか。クリスマスか」 「そう、お前の離婚記念日」 どうやら若先生はよりにもよってクリスマスに離婚したらしい。まだまだ子供の私はその当たりの事情を詳しく知らされてはいない。優しくておもしろい早季子さんがこの場所からいなくなってしまった、という事実でしか認識していない。 結婚しても離婚しても若先生はあまり変らなかったから、本当のところよくわからない。結婚ってそんなもんなのかな、って今でも不思議に思っている。 「あのな、親父がさぼる分、俺にしわ寄せがくるんだが」 「年寄りをあまりこきつかうでない」 「やかましい、こういう時だけ年寄りぶりやがって!」 本当に忙しくていらいらしっぱなしの若先生が食って掛かる。それを平然と受け止め、おいしそうに料理を頬張っている大先生。 「まあまあ、ここに来たってことは、一息ついたということだろうが」 「・・・・・・まあ、そうだけど」 「それに、香織ちゃんの事が気になって、来たんだろう??素直じゃないなぁ」 鼻の頭を掻きながら、ちょっとだけ若先生が口籠る。 その後はなんとなく加わった若先生と3人、楽しく過ごすことができた。 やっぱり誰かと一緒に食事をするのは楽しい。それが私の大好きな人だとしたら、なおさらだ。迷惑かもしれない、そう思いはするけれど、ここへ来ることをやめられない。 このままこの家の子供になれたらいいのに、そう思ったのはイヴの願いごと。 決して叶うことのない、願い。 これからもこの場所にいることができたなら。 ずっとずっとこのままでいたい、と。
12.13.2005
>>クリスマス小話・目次>>Homeline by Pearl Box |